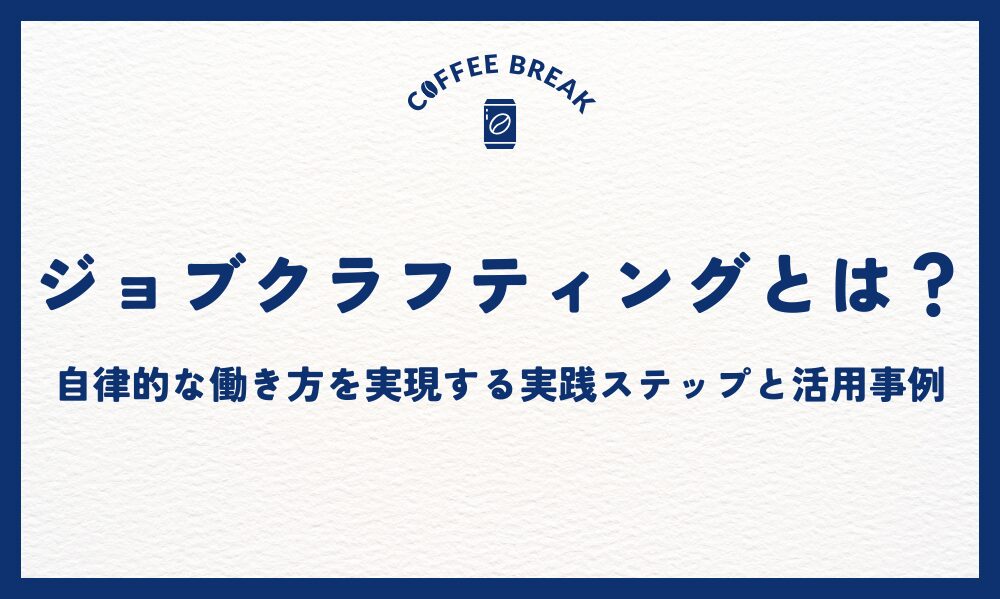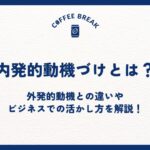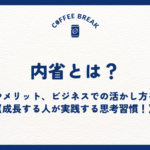近年、働き方の多様化が進むなかで、「自分の仕事にもっと意味ややりがいを感じたい」と考えるビジネスパーソンが増えています。そんな中注目を集めているのが「ジョブクラフティング」という概念です。これは、与えられた仕事に対して自ら工夫や再設計を加えることで、より主体的に、そして前向きに仕事に取り組むためのアプローチ。企業にとっても、従業員のエンゲージメント向上や離職率低下につながる可能性があるため、導入を検討する企業が増えています。
本記事では、ジョブクラフティングの定義や背景から具体的な実践方法、導入時のポイントや企業での活用事例までを幅広く解説します。ジョブクラフティングの理解を深め、自律的な働き方を実現するための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。
目次
ジョブクラフティングとは
「ジョブクラフティング」とは、与えられた仕事をそのまま受け入れるのではなく、自分自身の手で“再構築(クラフティング)”していくという考え方です。つまり、業務の内容や人間関係、仕事に対する見方を自らの工夫で変えることで、より自分らしく、やりがいを持って働くことを目指すアプローチです。
この概念は、「仕事を自分ごと化する力」と言い換えることもできるでしょう。上司や会社が一方的に決めた業務に従うのではなく、自分の強みや関心を活かしながら、日々の業務に前向きに関わっていくことで、仕事そのものの質や満足度が高まっていくという理論です。
仕事に対する主体的な関わり方
ジョブクラフティングの本質は「主体性」です。会社から与えられた職務を、ただこなすのではなく、自分で意味づけし直し、より自分にフィットする形に変える。この姿勢が、働きがいやモチベーションの向上に大きな影響を与えるとされています。
たとえば、営業職であれば、ただ商品を売ることにとどまらず、「お客様の課題解決に貢献する」ことを自分の仕事の目的と再定義することができます。このような意識の変化が、自発的な行動や創意工夫を生み出します。
提唱者と理論的な背景(アダム・グラントら)
ジョブクラフティングは、組織心理学の分野で注目されている理論で、アメリカの組織行動学者であるアダム・グラント氏やエイミー・レズネスキー氏らの研究によって提唱されました。彼らは、「人は仕事を通じて自己実現を目指す生き物である」という観点から、職務の再設計が働く人の心理や行動に与える影響を研究しています。
この考え方は、従来のトップダウン型の職務設計とは一線を画し、「従業員の主体性を尊重したボトムアップ型の働き方」として評価されています。
ビジネスで注目される理由と社会的背景(VUCA時代など)
ジョブクラフティングが近年ますます注目されている背景には、「VUCA」と呼ばれる変化の激しい時代環境があります。ビジネスを取り巻く状況が不確実かつ複雑になる中で、指示待ちでは対応できない場面が増えており、各自が主体的に動ける組織が求められています。
また、働き方改革やメンタルヘルスの重要性が叫ばれる今、自分らしく働くことへのニーズも高まっています。そうした流れの中で、ジョブクラフティングは「個人の幸福」と「組織の成果」を両立させる手段として、企業の人材戦略にも組み込まれつつあるのです。
仕事に対する主体性を高める方法として「内発的動機とは?外発的動機との違いやビジネスでの活かし方を解説」も参考になります。
ジョブクラフティングの3つの分類
ジョブクラフティングは、大きく3つの側面から分類されます。それぞれ「作業クラフティング」「人間関係クラフティング」「認知クラフティング」と呼ばれ、仕事に対する関わり方を多角的に見直すための視点を提供してくれます。これらをバランスよく活用することで、より充実した働き方を実現することができます。
作業クラフティングとは
作業クラフティング(Task Crafting)とは、日々の業務内容やその進め方に変化を加えることを指します。具体的には、タスクの順序を変えたり、新しい仕事を加えたり、逆に不要な仕事を減らしたりすることが含まれます。
たとえば、カスタマーサポート担当者が「マニュアル対応」から一歩踏み込み、「顧客に合わせた対応フローを自ら作る」ことで、作業内容の工夫を実現するケースがこれに当たります。自分なりのやり方を取り入れることで、仕事に対するオーナーシップが強まり、モチベーションも高まります。
人間関係クラフティングとは
人間関係クラフティング(Relational Crafting)は、職場での人間関係の構築や関わり方を見直す取り組みです。より協力的な同僚とチームを組む、新たな社内ネットワークを築く、他部署との連携を積極的に行うといった行動が該当します。
このクラフティングによって、信頼関係の強化や情報共有が促進されるだけでなく、心理的安全性が高まることで、創造的なアイデアや提案も生まれやすくなります。対人関係を自分からデザインする姿勢が、働きやすい環境づくりにつながります。
認知クラフティングとは
認知クラフティング(Cognitive Crafting)は、仕事そのものに対する「意味づけ」を変える取り組みです。仕事の価値や目的を再定義することで、自分にとって意義のある活動と認識することが可能になります。
たとえば、清掃員が「ただ掃除をしているのではなく、人々が快適に過ごせる空間を整えている」と考えるようになることで、仕事に対する誇りや責任感が生まれるというようなケースです。視点を変えるだけで、同じ仕事でも感じ方ややりがいが大きく変わります。
内省と仕事の捉え方については「内省とは?意味やメリット、ビジネスでの活かし方を解説」も参考になります。
ジョブクラフティングのやり方・実践ステップ
ジョブクラフティングは「考え方」だけでなく、実際に行動に落とし込むことが大切です。ここでは、誰でも取り組めるような具体的な実践ステップを3段階に分けて紹介します。個人で行う場合も、チームで行う研修においても応用可能なプロセスです。
STEP1:業務の洗い出しと自己分析
最初のステップは、現在自分が担っている仕事を 可視化 することです。具体的には、1日の業務内容を細かく書き出し、それぞれのタスクにどの程度の時間やエネルギーを使っているか、どれだけやりがいを感じているかを自己評価します。
次に、「自分がどんなことにやりがいを感じるのか」「得意・苦手な業務は何か」「どんな働き方が心地よいか」といった 自己分析 を行いましょう。このプロセスが、自分にとってどの業務が意味のあるものなのかを見つけるきっかけになります。
STEP2:仕事の再設計と人間関係の調整
次に行うのは、洗い出した業務の中で 改善できるポイントを見つけ出し、再設計 する作業です。タスクの優先順位を見直したり、新しいやり方にチャレンジしたりすることで、「作業クラフティング」を実行できます。
加えて、「この人ともっと連携したい」「新しい視点を得るために別部署の人と話してみたい」など、 人間関係の再構築(人間関係クラフティング) も視野に入れましょう。周囲との関わり方を変えることで、業務全体の見え方も大きく変わります。
STEP3:実践・フィードバック・振り返り
クラフティングの内容が決まったら、 実際に行動してみることが大切 です。そして、ある程度の期間が経った後に、その変化がどのような影響を与えたかを 振り返る ことで、さらに効果的なジョブクラフティングにつなげることができます。
できれば、上司や同僚などのフィードバックも取り入れることで、自分では気づけなかった変化や新しい可能性を知ることができます。この繰り返しによって、自分に最も合った働き方が見えてきます。
ワークショップ形式で学ぶジョブクラフティング(図解・研修への応用)
企業によっては、ジョブクラフティングを ワークショップ形式で導入 しているケースもあります。参加者が業務を書き出し、グループディスカッションを通じて互いの考え方を共有し、視野を広げることができるため、非常に実践的です。
このような研修では、以下のような図解を使うことが効果的です:
| ステップ | 内容 | 主な狙い |
|---|---|---|
| ステップ1 | 業務の棚卸し | 自己認識を深める |
| ステップ2 | 再設計 | 主体的な関わり方の発見 |
| ステップ3 | 実践と振り返り | 持続可能な改善の定着 |
社内での導入を検討している場合は、ジョブクラフティングをテーマとしたファシリテーションや、コーチングの導入もおすすめです。
ジョブクラフティングの効果とメリット
ジョブクラフティングは、ただ「仕事を変える」だけではなく、働く人の心理的・組織的な側面にも多大な影響を与える手法です。ここでは、ジョブクラフティングによって得られる主な効果とメリットについて解説します。
ワークエンゲージメントの向上
ジョブクラフティングの最も顕著な効果のひとつが、 ワークエンゲージメントの向上 です。ワークエンゲージメントとは、仕事に対する熱意・没頭・活力のことを指し、従業員が仕事に積極的かつ前向きに取り組んでいる状態を表します。
自分の意思で仕事の進め方を変えたり、意味づけを再定義したりすることで、「やらされている仕事」から「自分が選んで取り組んでいる仕事」へと認識が変化します。この自律的な感覚が、モチベーションの向上と深いつながりを持っています。
生産性・創造性のアップ
ジョブクラフティングによって、従業員は自らの強みや得意分野を仕事に活かせるようになります。その結果、 生産性が向上するだけでなく、新しいアイデアや提案が生まれやすくなる という創造性の側面にもプラスの影響があります。
たとえば、単純作業の中に改善点を見出して業務プロセスを変革したり、顧客対応の中で新しいサービス提案を思いついたりと、業務改善やイノベーションの種が生まれやすくなるのです。
自発性と離職率低下に与える影響
ジョブクラフティングによって生まれる「仕事に対する納得感」や「自己効力感」は、従業員の 自発性を高める とともに、 離職率の低下 にも貢献します。
特に、若手社員やミレニアル世代・Z世代といった「仕事の意義」を重視する層にとって、ジョブクラフティングは自律的にキャリアを築く手段として有効です。逆に、職務に対して無関心・無力感を持っている状態では、離職や燃え尽き症候群につながりやすくなります。
実際に、ジョブクラフティングを積極的に取り入れている企業では、従業員の定着率や満足度が向上したという報告もあります。人材の定着が企業の競争力に直結する現代において、ジョブクラフティングは重要な人材戦略の一部となりつつあるのです。
ワークエンゲージメントを高める方法について詳しくは「レジリエンスを高める実践ステップ!ビジネスの逆境に負けない”折れない心”の育て方」も役立つでしょう。
ジョブデザインとの違い
ジョブクラフティングとよく比較される概念に「ジョブデザイン」があります。どちらも「仕事の設計」に関わる考え方ですが、そのアプローチや主体は大きく異なります。ここでは、両者の違いを明確にし、どのように使い分けるべきかを解説します。
トップダウン型とボトムアップ型の比較
ジョブデザインは、企業や上司といった 組織側が主体となって職務の設計を行う 「トップダウン型」のアプローチです。業務の内容や役割、責任範囲、報酬制度などを管理側が計画・設計し、それに基づいて従業員が働くというスタイルです。典型的には職務記述書(ジョブディスクリプション)がその成果物になります。
一方、ジョブクラフティングは 従業員自身が仕事を再設計する 「ボトムアップ型」のアプローチです。日々の業務に対する感じ方や進め方を、自らの裁量で調整していくため、柔軟性があり、個人の価値観や強みに合わせやすいのが特徴です。
| 項目 | ジョブデザイン | ジョブクラフティング |
|---|---|---|
| 主体 | 組織(マネジメント側) | 個人(従業員自身) |
| アプローチ | トップダウン型 | ボトムアップ型 |
| 目的 | 職務の効率化・標準化 | やりがい・働きがいの向上 |
| 柔軟性 | 低め(制度・構造中心) | 高め(個人の工夫に基づく) |
自律性を重視するか、役割設計を重視するか
ジョブデザインは、業務の 明確化と標準化 によって、組織としての効率や一貫性を担保することが目的です。特に大企業や製造業など、業務が複雑で多人数が関わる環境では、必要不可欠な設計手法です。
一方で、ジョブクラフティングは 自律性と意味づけ を重視します。変化が激しい環境や、創造性・個人の裁量が求められる職種においては、ジョブクラフティングのような柔軟な働き方が適しているといえるでしょう。
つまり、ジョブデザインとジョブクラフティングは対立するものではなく、 目的に応じて併用できる関係 にあります。まずはジョブデザインで基本の枠組みを作り、その中で従業員がジョブクラフティングを通じて自分らしく働くことで、組織としての整合性と個人の充実感を両立することが可能です。
ジョブクラフティングの活用事例と研修例
ジョブクラフティングは、理論的な枠組みにとどまらず、実際のビジネスの現場でも導入が進んでいます。ここでは、国内外の具体的な実践事例や、企業内での研修例を紹介しながら、その有効性と応用方法を解説します。
ディズニー社の実践事例
ジョブクラフティングの代表的な事例としてよく紹介されるのが、 ウォルト・ディズニー・カンパニー のスタッフです。たとえば、清掃スタッフ(カストーディアル)たちは、ただ園内を掃除するのではなく、「来園者に魔法のような体験を提供する仕事」として自身の役割を再定義しています。
彼らは来園者とのコミュニケーションを積極的に行ったり、時にはパフォーマンスを交えて対応するなど、自発的に仕事を“再設計”しています。このような姿勢が、ディズニーブランドの高い顧客満足度を支える一因となっているのです。
厚労省の報告と活用可能性
日本国内でもジョブクラフティングの有効性に注目が集まっており、 厚生労働省の働き方改革関連報告書 の中でも、従業員の主体性向上の手段として取り上げられるようになっています。
特に、コロナ禍以降のリモートワーク環境下では、業務が見えにくくなることへの対応策として、「自律的に業務をコントロールする力」が求められています。その観点から、ジョブクラフティングは多くの企業にとって現実的かつ必要性の高い施策といえるでしょう。
詳しくは 厚生労働省「労働経済の分析(令和元年)」 をご覧ください。
企業で行うジョブクラフティング研修の流れ
多くの企業では、ジョブクラフティングの考え方を社員に浸透させるために 研修プログラム を導入しています。以下は、一般的な研修の流れです:
- イントロダクション:ジョブクラフティングの理論と背景を学ぶ
- 自己分析ワーク:現業務の棚卸し、価値観・強みの整理
- クラフティング設計:どのように業務・関係・認知を再設計するかのプラン作成
- 共有・フィードバック:他の参加者と意見交換しながら視野を広げる
- アクションプラン作成:実践に向けた具体的な行動目標の設定
このようなワークショップ形式の研修は、部署単位や職種別にカスタマイズされることが多く、導入企業のカルチャーに合わせた設計が可能です。
導入時の注意点と課題
ジョブクラフティングは非常に柔軟性の高い手法であり、多くのメリットがありますが、導入にあたっては注意すべき点や課題も存在します。組織として取り入れる際には、これらの点を理解し、適切に対処することが成功のカギとなります。
属人化と組織の一体感のバランス
ジョブクラフティングの性質上、個人が自由に仕事を設計できる反面、 仕事の属人化 が進みすぎると、チーム全体の一体感や組織の方向性にズレが生じる可能性があります。
たとえば、ある社員が自分の興味関心に合わせて仕事の進め方を大きく変えた結果、チーム内の連携が取りづらくなったり、業務プロセスが不統一になるといったケースも考えられます。そこで重要になるのが、「個人の自由」と「組織の整合性」のバランスです。
企業としては、一定のガイドラインや目的共有を行いながら、自由度を確保することが求められます。
上司・マネージャーの関わり方
ジョブクラフティングの成功には、 上司やマネージャーの理解と支援 が不可欠です。上司が旧来のトップダウン型のマネジメントに固執していると、従業員がクラフティングを試みても否定され、意欲を失ってしまう可能性があります。
理想的なのは、上司が部下に対して「あなたがどうしたいか?」を問いかけ、内省を促しながら適切なフィードバックを行う関わり方です。エンパワーメント型のマネジメントが、ジョブクラフティングを組織全体に浸透させる鍵となります。
短期的成果を求めすぎない工夫
ジョブクラフティングは、従業員のモチベーションや働き方に徐々に変化をもたらす中長期的な施策です。そのため、「すぐに成果を出さなければ」と 短期的な効果を過度に求めることは逆効果 となることがあります。
特に人事部門や経営層は、導入効果を評価する際に「数値」や「生産性の即時向上」に目が行きがちですが、初期段階では従業員の意識変化や行動変容など、 定性的な成果にも目を向けること が大切です。
導入から効果が定着するまでには一定の時間がかかるため、継続的なモニタリングと改善を前提とした取り組みが必要となります。
よくある質問(Q&A)
ここでは、ジョブクラフティングに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。初めて耳にする方から導入を検討している企業担当者まで、幅広い疑問にお答えします。
ジョブクラフティングとはどういう考え方ですか?
ジョブクラフティングとは、 従業員が自らの仕事に対して主体的に工夫を加え、意味ややりがいを再構築していく考え方 です。与えられた業務をそのままこなすのではなく、自分の強みや興味を活かして、仕事内容・人間関係・認識の仕方を自分流にアレンジするアプローチといえます。
ジョブクラフティングの効果を高めるには?
効果を高めるためには、以下のような工夫が有効です:
- 自己分析の徹底:自分の価値観・強み・理想の働き方を明確にする
- フィードバックの活用:上司や同僚からの意見を取り入れながら改善を重ねる
- 継続的な振り返り:クラフティングの効果や課題を定期的に見直す
また、組織側も一定の自由度を認め、心理的安全性のある環境を整えることが重要です。
ジョブデザインとどう違うの?
ジョブデザインは、 会社や上司が業務内容や役割を設計する「トップダウン型」 の手法。一方、ジョブクラフティングは、 従業員が自ら業務の進め方や意味づけを変える「ボトムアップ型」 のアプローチです。
両者は目的が異なりますが、併用することでより効果的な人材活用が可能になります。
どんな職種・立場に向いている?
基本的には どの職種でも活用可能 ですが、特に次のような場面で効果が発揮されやすいです:
- 自由度が高く、裁量のある職種(例:営業、企画、クリエイティブ職)
- 変化が激しい職場環境にある職種
- 若手や中堅社員のモチベーション低下を防ぎたい場面
また、マネージャー層が部下の働き方を支援する際にも有効な視点となります。
ジョブクラフティングの研修はどう進める?
研修は ワークショップ形式 で行われることが多く、以下のような構成が一般的です:
- 理論理解:ジョブクラフティングの基本を学ぶ
- 自己分析:業務の棚卸しと価値観の確認
- 再設計ワーク:自分の業務の見直しプランを考える
- 共有・発表:他の参加者とアイデアを共有し学びを深める
この形式により、自分だけでなく他者の視点からも学びを得ることができます。
まとめ|ジョブクラフティングで自律的に働く組織をつくる
ジョブクラフティングは、「自分の仕事に意味を持たせ、自分らしく働く」ことを可能にするアプローチです。変化の激しいビジネス環境や、働き方の多様化が進む現代において、ただ与えられた業務をこなすだけでは、モチベーションやパフォーマンスの維持が難しくなってきています。
そんな中、ジョブクラフティングは個人にとっては「やりがいを再発見する手段」、企業にとっては「エンゲージメントと成果を高める人材開発施策」として大きな注目を集めています。
導入には、上司の理解や組織文化の支援体制などの準備が必要ではありますが、それを乗り越える価値は十分にあります。とくに、次世代リーダーの育成や離職防止、組織の創造性向上を目指す企業には非常に効果的です。
まずは小さな一歩から。自分の仕事に目を向け、「どのように関わり方を変えられるか?」を考えてみること。それがジョブクラフティングの第一歩であり、組織の変革のきっかけにもなります。