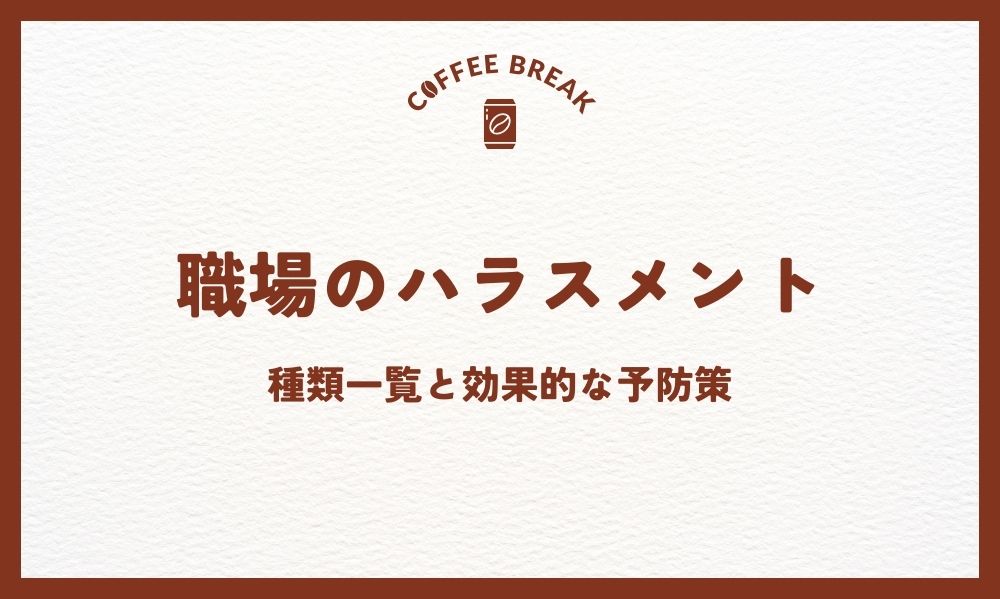近年、職場におけるハラスメント問題は深刻化しており、企業にとって適切な対応が求められています。2019年のパワハラ防止法制定以降、ハラスメント対策は企業の法的義務となり、さらに新しい種類のハラスメントも次々と認識されるようになりました。本記事では、2025年最新版の職場で知っておくべきハラスメントの種類を一覧で解説するとともに、組織として取り組むべき効果的な予防策についてご紹介します。人事担当者や管理職の方々にとって、ハラスメントのない健全な職場づくりのためのガイドとしてお役立てください。
目次
1. ハラスメントとは?基本的な定義と概念
ハラスメントとは、相手に対して精神的・身体的な苦痛を与える、または不快感を抱かせる言動や行為を指します。職場におけるハラスメントは、個人の尊厳を傷つけるだけでなく、職場環境を悪化させ、企業の生産性低下やイメージダウンにもつながる重大な問題です。
ハラスメントは時代とともに変化し、社会的認識も拡大しています。かつては「いじめ」や「嫌がらせ」として軽視されがちだった行為も、現在では明確に「ハラスメント」として認識され、法的対応が求められるようになりました。
特に重要なのは、ハラスメントの判断基準は「行為者の意図」ではなく「被害者の受け止め方」にあるという点です。「冗談のつもり」「指導の一環」という言い訳は通用せず、相手が不快に感じれば、それはハラスメントとなり得ます。
2. 法令で定義されている主要なハラスメント
現在、日本の法令で明確に定義されているハラスメントには主に以下の3つがあります。これらは「職場の三大ハラスメント」とも呼ばれ、企業には防止措置が義務付けられています。
2-1. パワーハラスメント(パワハラ)
パワーハラスメントは、労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)によって明確に定義されています。「職場における優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」であり、「労働者の就業環境が害される」ものとされています。
パワハラは以下の6類型に分類されます:
パワハラの認定には、「優越的な関係」「業務上の適正範囲を超えること」「環境が害されること」の3つの要素が必要です。上司と部下の関係だけでなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司へのいわゆる「逆パワハラ」も成立します。
2-2. セクシュアルハラスメント(セクハラ)
セクシュアルハラスメントは、男女雇用機会均等法により定義されており、「職場において行われる労働者の意に反する性的な言動」で、それに対する労働者の対応によって労働条件に不利益を受けたり、就業環境が害されたりするものを指します。
セクハラには主に2種類あります:
- 対価型セクハラ:性的な要求に対する労働者の対応(拒否や抵抗)によって、解雇、降格、減給などの不利益を受けること
- 環境型セクハラ:性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、就業する上で見過ごせない程度の支障が生じること
セクハラは男性から女性へだけでなく、女性から男性、同性間でも成立します。また、LGBTQなどの性的マイノリティに関連する言動もセクハラとなり得ることに注意が必要です。
2-3. 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタハラ・パタハラ)
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントは、男女雇用機会均等法および育児・介護休業法によって定義されています。女性労働者の妊娠・出産に関連したハラスメントをマタニティハラスメント(マタハラ)、男性労働者の育児休業取得に関連したハラスメントをパタニティハラスメント(パタハラ)と呼びます。
具体的には以下のような行為が該当します:
マタハラの例
・妊娠を報告したら「迷惑だ」と言われた
・妊娠を理由に望まない異動を命じられた
・産休・育休の取得を控えるよう言われた
・妊娠中の体調不良を配慮せず、通常通りの業務を強要された
パタハラの例
・男性が育児休業の取得を申し出たところ、「男のくせに」と非難された
・育児休業を取得したことで昇給や昇進で不利な扱いを受けた
・育児のための時短勤務を認めない
・育児に関する制度の利用を阻害された
3. 職場で問題となる新たなハラスメントの種類
法令で明確に定義されたハラスメント以外にも、職場で問題となる様々なハラスメントが認識されています。ここでは、特に注目されている新しい種類のハラスメントを紹介します。
3-1. カスタマーハラスメント(カスハラ)
カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先からの著しい迷惑行為を指します。厚生労働省は2020年に「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表し、企業に対応策の検討を促しています。

カスハラの具体例:
- 理不尽なクレームを長時間にわたって繰り返す
- 店員に対する暴言や侮辱的な言動
- セクシュアルな言動や不必要な接触
- SNSでの誹謗中傷や個人情報の暴露
3-2. リモートハラスメント(リモハラ)
リモートワークの普及に伴い認識されるようになった新しいタイプのハラスメントです。オンライン環境特有の問題に起因します。
リモハラの具体例:
- Web会議での不適切な服装や背景
- オンライン会議中の無断録音・録画
- 終業後や休日の頻繁な連絡や業務指示
- リモートワーク中の過剰な監視や報告の要求
- オンライン会議での一方的な意見の遮断や無視
3-3. テクノロジーハラスメント(テクハラ)
テクノロジーハラスメントは、ITリテラシーの差を利用した嫌がらせや差別を指します。デジタル化が進む現代の職場で特に問題になっています。

3-4. ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)
ジェンダーハラスメントとは、性別に基づく固定観念や偏見による差別的言動を指します。セクハラとは異なり、直接的な性的言動ではなく、性別の役割規範に関連した言動が問題となります。
ジェンハラの具体例:
- 「女性なのに」「男のくせに」といった発言
- 女性だけにお茶くみや掃除を要求する
- 性別だけを理由に特定の業務から除外する
- 性別に基づいたステレオタイプな冗談を言う
3-5. ロジカルハラスメント(ロジハラ)
ロジカルハラスメントとは、論理性を振りかざして相手を追い詰める言動のことです。一見合理的な指摘のように見えますが、実際は相手を否定したり威圧したりする目的で行われます。
ロジハラの具体例:
- 些細なミスを論理的に責め立てる
- 自分の意見だけを正論と主張し、相手の意見を否定する
- 論理的思考を強要し、感情面を全く考慮しない
- 専門知識を振りかざして相手を黙らせる
3-6. 時短ハラスメント(ジタハラ)
時短ハラスメントとは、育児や介護などによる時短勤務者に対する嫌がらせを指します。ワークライフバランスを重視する社会になるにつれて問題視されるようになりました。
ジタハラの具体例:
- 「楽していいね」「特別扱いだ」などの発言
- 時短勤務者に対する仕事の依頼を避ける
- 時短勤務者を会議や情報共有から除外する
- 定時で帰ることを非難する言動
3-7. モラルハラスメント(モラハラ)
モラルハラスメントとは、言葉や態度による精神的な攻撃を指します。身体的な暴力を伴わないため表面化しにくく、被害者が気づきにくい点が特徴です。
4. 2025年現在把握すべきハラスメント一覧表
以下に、2025年現在で職場において把握しておくべき主要なハラスメントを一覧表にまとめました。法的定義の有無や対策の必要性を併せて確認できます。
| ハラスメント名 | 略称 | 法的定義 | 対策義務 | 主な被害場面 |
|---|---|---|---|---|
| パワーハラスメント | パワハラ | あり | あり | 業務指示・評価 |
| セクシュアルハラスメント | セクハラ | あり | あり | 職場の人間関係 |
| マタニティハラスメント | マタハラ | あり | あり | 妊娠・出産時 |
| パタニティハラスメント | パタハラ | あり | あり | 育児休業取得時 |
| カスタマーハラスメント | カスハラ | ガイドラインあり | 努力義務 | 顧客対応 |
| モラルハラスメント | モラハラ | なし | なし | 日常のコミュニケーション |
| ジェンダーハラスメント | ジェンハラ | なし | なし | 性別に関する場面 |
| テクノロジーハラスメント | テクハラ | なし | なし | ITツール使用時 |
| リモートハラスメント | リモハラ | なし | なし | リモートワーク |
| 時短ハラスメント | ジタハラ | なし | なし | 時短勤務時 |
| ロジカルハラスメント | ロジハラ | なし | なし | 議論・意思決定時 |
| アルコールハラスメント | アルハラ | なし | なし | 飲み会・接待 |
| スメルハラスメント | スメハラ | なし | なし | 日常の職場環境 |
| エイジハラスメント | エイハラ | なし | なし | 年齢に関する場面 |
| ケアハラスメント | ケアハラ | なし | なし | 介護休業取得時 |
※ハラスメントの種類は今後も増加する可能性があります。定期的な情報収集が重要です。
5. ハラスメントが企業にもたらす深刻な影響
ハラスメントは被害者個人だけでなく、企業全体に大きな損失をもたらします。以下にその影響をいくつか紹介します。
5-1. 従業員の心身への悪影響
ハラスメントを受けた従業員は、精神的ストレスを抱え、最悪の場合うつ病などの精神疾患を発症することもあります。休職や退職につながるケースも少なくなく、組織全体の士気低下にもつながります。
厚生労働省の調査によれば、ハラスメントを受けた従業員の約40%が「仕事に対する意欲が減退した」と回答しており、約20%が「体調を崩した」と答えています。
5-2. 企業の法的リスクと経済的損失
ハラスメント問題が訴訟に発展すると、企業は以下のような経済的損失を被る可能性があります:
特に近年は、SNS等でハラスメント問題が拡散されるリスクも高まっており、企業の評判に長期的なダメージを与える可能性があります。
5-3. 組織風土・生産性への影響
ハラスメントが放置される職場では、コミュニケーションが阻害され、従業員間の信頼関係が崩れます。そのような環境ではイノベーションや創造性が育まれず、組織全体の生産性が低下します。
また、こうした負の職場環境は「ブラック企業」というレッテルにつながり、優秀な人材の採用が困難になるという悪循環を生み出します。
6. ハラスメントに関する最新の法改正と企業の義務
ハラスメント対策に関する法制度は近年大きく強化されています。ここでは、企業が把握すべき最新の法改正と義務について解説します。
6-1. パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の全面施行
2019年に成立した「改正労働施策総合推進法」(通称:パワハラ防止法)は、大企業に対しては2020年6月から、中小企業に対しては2022年4月から全面施行されました。
主な義務内容は以下の通りです:
- 事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
- 相談窓口の設置等の相談体制の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応
- 相談者・行為者のプライバシー保護、相談者への不利益な取り扱いの禁止
6-2. セクハラ・マタハラ対策の強化
男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の改正により、セクハラとマタハラに関する対策も強化されています。特に注目すべき点は以下の通りです:
セクハラ・マタハラ対策における重要ポイント
- セクハラの行為者に対する事業主による厳正な対処の明記
- プライバシー保護や不利益取扱いの禁止規定の強化
- 相談対応体制の整備義務の明確化
- 他社の労働者からのセクハラに関する配慮義務の新設
- パタハラ(男性の育児休業取得に関するハラスメント)防止措置の義務化
6-3. 就活生に対するハラスメント防止
2020年の改正法では、就職活動中の学生等に対するセクハラ防止も事業主の義務として明確化されました。企業は採用活動中の学生に対しても、従業員と同様にハラスメント防止措置を講じる必要があります。
特に面接や説明会などの場面での言動に注意が必要で、採用担当者への研修も重要です。
6-4. カスタマーハラスメント対策の推進
顧客や取引先からの著しい迷惑行為(カスハラ)についても、企業が対策を講じることが努力義務として明確化されました。事業主は以下のような対応を行うことが求められています:
- 社内での対応方針の明確化と周知
- マニュアル等の作成と研修の実施
- 被害者への適切な配慮と支援
- 必要に応じた警察等との連携体制の構築
7. 効果的なハラスメント予防策と対応方法
ハラスメントの発生を未然に防ぎ、発生した場合にも適切に対応するために、企業が取り組むべき予防策と対応方法を解説します。
7-1. 企業方針の明確化と周知
ハラスメント対策の第一歩は、企業としての方針を明確に定め、全従業員に周知することです。
実施すべき具体的な取り組み:
- ハラスメント禁止方針の策定:経営トップのメッセージを含めた明確な方針を策定
- 就業規則への明記:ハラスメント行為を懲戒対象として明記
- 定期的な方針の周知:社内報やイントラネット、ポスター等での継続的な周知
- トップのコミットメント:経営層からのメッセージ発信による姿勢の明確化
7-2. 定期的な研修・教育の実施
ハラスメントに関する理解を深め、適切な行動を促すための研修は非常に重要です。
効果的な研修のポイント:

- 階層別研修:管理職向け、一般社員向けなど対象に合わせた内容
- 事例を用いた研修:具体的な事例を元にしたケーススタディ
- 参加型研修:ロールプレイやグループディスカッションを取り入れた実践的な内容
- 新入社員研修での実施:入社時点からの意識付け
- eラーニングの活用:時間や場所を選ばず受講できる環境の整備
7-3. 相談窓口の設置と適切な対応
ハラスメントの早期発見と適切な対応のためには、従業員が安心して相談できる窓口の設置が不可欠です。
効果的な相談窓口の条件:
- 複数の相談窓口:社内・社外、男性・女性など選択できる体制
- 専門知識を持った担当者の配置:適切なカウンセリングとアドバイスができる人材
- プライバシー保護の徹底:相談内容の秘密保持
- 不利益取扱いの禁止:相談者への報復行為の禁止
- 相談しやすい環境づくり:アクセスのしやすさや匿名性の確保
7-4. 迅速かつ適切な事後対応
ハラスメントが発生した場合、または相談があった場合には、迅速かつ適切な対応が求められます。
適切な事後対応のステップ:
7-5. ハラスメントが発生しにくい職場環境づくり
ハラスメント対策の根本的な解決策は、そもそもハラスメントが発生しにくい職場環境を構築することです。
健全な職場環境のための取り組み:
8. ハラスメントに関するよくある疑問と回答
最後に、ハラスメントに関してよく寄せられる疑問に回答します。
ハラスメントの種類は多すぎるのではないでしょうか?
確かに近年、新しいタイプのハラスメントが次々と認識されるようになり、「〇〇ハラ」という言葉が増加していることへの懸念の声もあります。しかし、これは社会が多様性を尊重し、一人ひとりの尊厳をより重視するようになった証でもあります。
重要なのは名称ではなく、「相手を不快にさせる言動」という本質を理解し、敬意を持って接することです。過度に神経質になるのではなく、良識ある行動と相互理解を心がけることが大切です。
部下への指導とパワハラの境界線はどこにありますか?
部下への指導とパワハラの最大の違いは「業務上の必要性と相当性」です。業務の目的を達成するために必要かつ相当な範囲内の指導はパワハラには当たりません。
以下のポイントに注意して指導することが重要です:
- 指導の目的と内容を明確にする
- 感情的にならず冷静に対応する
- 人格を否定するような発言を避ける
- プライベートに過度に踏み込まない
- 公開の場での過度な叱責を避ける
- 相手の成長を目的とした建設的な指導を心がける
ハラスメントの被害を受けたらどうすればよいですか?
ハラスメントの被害を受けた場合は、以下の対応を検討してください:
- 記録を残す:日時、場所、内容、証人の有無などを記録しておく
- 社内の相談窓口に相談する:人事部や専用窓口がある場合はそちらに相談
- 信頼できる上司や同僚に相談する:状況に応じて身近な人に相談
- 外部の相談窓口を利用する:都道府県労働局や労働基準監督署などの公的機関に相談
- 医療機関を受診する:心身に不調がある場合は早めに専門家に相談
一人で抱え込まず、早めに相談することが重要です。
中小企業でもハラスメント対策は必要ですか?
はい、中小企業も含めたすべての企業にハラスメント対策が義務付けられています。2022年4月からはパワハラ防止法が中小企業にも適用され、セクハラやマタハラの防止措置も同様に義務化されています。
人員や予算に制約がある中小企業では、以下のような取り組みから始めることができます:
- 経営者自らが率先してハラスメント防止の姿勢を示す
- 無料の研修教材や資料(厚生労働省提供)を活用する
- 複数の相談窓口を設けるなど、身近な環境で相談できる体制を整える
- 外部の専門機関と連携して対応する
9. まとめ:ハラスメントのない職場づくりに向けて
本記事では、2025年最新のハラスメントの種類と企業が取り組むべき対策について解説しました。ハラスメントの種類は時代とともに増加していますが、その根底には「相手の尊厳を傷つける行為」という共通点があります。
企業にとってハラスメント対策は、法令遵守のためだけでなく、組織の生産性向上や人材確保、企業価値の維持向上にもつながる重要な取り組みです。
ハラスメントのない職場を実現するためには、以下の3つのポイントが重要です:
- 知識と理解:ハラスメントの種類や定義について正しく理解する
- 予防と対策:適切な研修や相談体制の整備など、予防策を講じる
- 組織文化の醸成:互いを尊重し合う健全な職場環境を作る
一人ひとりが相手を尊重し、組織全体でハラスメント防止に取り組むことで、誰もが安心して能力を発揮できる職場を実現しましょう。
最後に、ハラスメント対策は「やらされ感」ではなく、組織の成長と発展のための積極的な投資という視点で取り組むことが重要です。ハラスメントのない職場は、従業員のエンゲージメント向上や創造性の発揮、そして企業の持続的成長につながります。