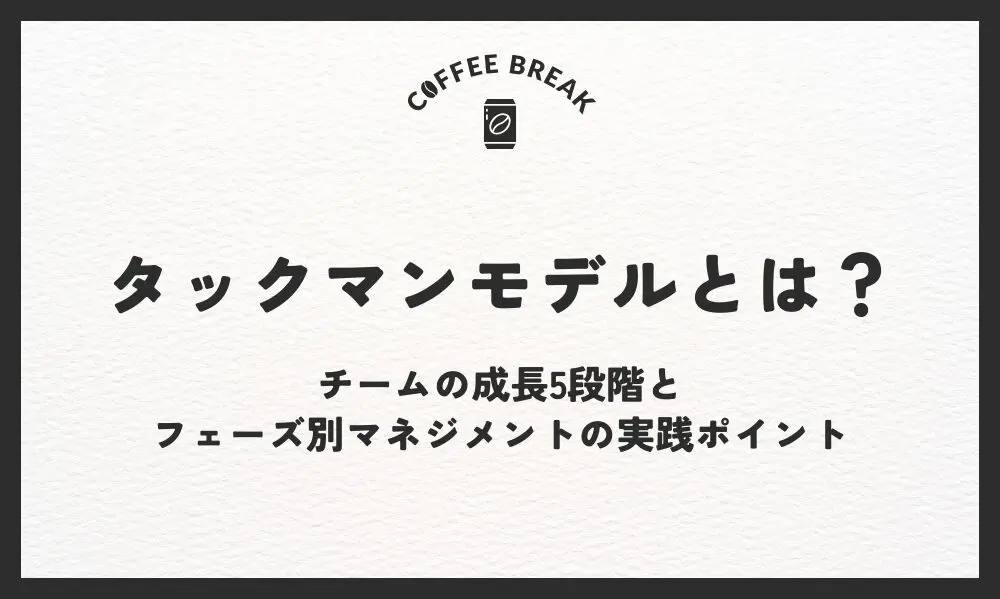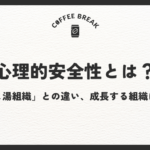チームでプロジェクトを進める中で、「なんだか空気が合わない」「最近まとまってきたかも」と感じることはありませんか?
それ、実はチームが成長する段階=「チームビルディングのフェーズ」かもしれません。
今回ご紹介する「タックマンモデル」は、チームの発展過程を5つのステージに分け、どの段階にいるのかを“見える化”できる理論です。
これを知ることで、チームに必要なコミュニケーションやマネジメントのヒントが見えてきます。
この記事では、タックマンモデルの基本から実践例、限界、そして自分のチームを診断するチェックリストまで、わかりやすく解説していきます。
目次
タックマンモデルとは?5つのステージでチームの成長を見える化
タックマンモデルの定義と成り立ち
タックマンモデルとは、1965年にアメリカの心理学者ブルース・W・タックマンが提唱した「チームの成長ステージに関する理論」です。彼は、チームが成熟していく過程を5つの段階に分類しました。
このモデルの基本的な考え方は、どんなチームも以下の順番で変化していくというものです。
- 形成期(Forming)
- 混乱期(Storming)
- 統一期(Norming)
- 機能期(Performing)
- 散会期(Adjourning)※後に追加
これらのステージは、単なる理論ではなく、実際のチームマネジメントに活かせる「道しるべ」として使うことができます。
チームのどのフェーズにいるのかを認識することで、適切なマネジメントや支援が可能になります。
また、企業のプロジェクトチームから教育現場、医療現場まで、さまざまな分野で応用されており、実用性の高い理論として知られています。
提唱者タックマンと理論の背景
タックマンモデルを提唱したのは、アメリカの心理学者ブルース・W・タックマン(Bruce Wayne Tuckman) です。彼は1965年に発表した論文「Developmental Sequence in Small Groups(小グループにおける発達的シーケンス)」において、チームの成長過程を4つのステージで定義しました(当初は形成期・混乱期・統一期・機能期の4段階)。
その後、1977年にMary Ann Jensenと共同で第5のステージ「散会期(Adjourning)」を追加し、現在の5ステージモデルが完成しました。
この理論は、当時から教育現場やグループダイナミクス研究において注目されていましたが、1980年代以降、ビジネス分野や組織開発(OD) の文脈でも高く評価されるようになります。特に、プロジェクトマネジメントやチームビルディングが重視されるようになった現代において、その有効性が再確認されています。
タックマンが重視したのは、「グループの発展は自然発生的なプロセスであり、リーダーシップや環境要因によって大きく左右される」という点です。そのため、彼の理論は単に段階を示すだけでなく、リーダーやマネージャーがどのように関わるかという実践的な指針としても使えるよう設計されています。
この理論が今でも活用され続けている理由
タックマンモデルは、提唱から半世紀以上経った今でも、多くの企業や教育現場、医療機関などで活用され続けています。その理由は大きく3つあります。
1. シンプルで直感的に理解しやすい構造
5つの段階が「形成 → 混乱 → 統一 → 機能 → 散会」という流れで整理されており、どのフェーズでも具体的なチームの状態がイメージしやすくなっています。そのため、マネージャーやチームリーダーが直感的に「いま何が起きているか」を把握しやすいのが特長です。
2. 多様な現場に適用できる汎用性
ビジネスチームだけでなく、プロジェクトごとに編成される一時的なチーム、教育現場のクラス、看護師のチーム、NPO活動など、さまざまな「人が集まる現場」に応用できるのもポイントです。リモートワークや国際チームなど、時代に合わせた働き方でも応用が可能です。
3. リーダーの判断材料として使いやすい
各ステージにはそれぞれチームが直面する課題や状態、そしてリーダーが取るべき行動の指針が明確に示されています。そのため、リーダーが「今は待つべきか」「介入すべきか」など、タイムリーな判断をするためのツールとしても有効です。
このように、タックマンモデルは 「変わるチーム」と「変わらない本質」 の両方を捉えられる柔軟な理論として、今日でも支持され続けています。
チームマネジメントの具体的な手法については「チームマネジメントの全体像!必要なスキルから成功事例まで徹底解説」も合わせてご覧ください。
チームの成長が一目でわかる!タックマンモデルの5ステージ解説
| ステージ名 | 状態の特徴 | チームの雰囲気 | リーダーの役割 |
|---|---|---|---|
| 形成期 | メンバーが探り合い | よそよそしい、表面的な関係 | 方向性・目的の明確化、信頼構築 |
| 混乱期 | 意見の対立や摩擦が起きる | 緊張・衝突が表面化 | 対立の調整、対話の促進 |
| 統一期 | ルールや信頼関係が固まり始める | 協力的、建設的な雰囲気 | 自律支援、共通ルールの育成 |
| 機能期 | 目標に向けて協働が進む | パフォーマンス最大化 | 最小限の介入で成果の後押し |
| 散会期 | チームの役割が終わる | 感謝・達成感・時に寂しさ | 振り返りと次のステップへの支援 |
ステージ1|形成期(Forming)
この段階の特徴とリーダーが取るべき行動
形成期は、チームが発足したばかりの「お互いを探っている」時期です。メンバー同士はまだ距離感があり、表面上は穏やかでも、本音を出せていない“よそよそしさ” が漂うことが多いのが特徴です。
このフェーズでは、以下のような状態が見られます:
- メンバーがお互いを観察し、様子をうかがっている
- 役割や責任が曖昧なまま活動が始まる
- 誰がリーダーシップを取るべきかがまだ定まらない
- チームとしての方向性が不透明
この段階でリーダーが果たすべき役割は非常に重要です。明確なビジョンやルールを設定し、メンバーが安心して関われる「心理的安全性の高い場」をつくることが求められます。
リーダーがやるべき具体的アクション
- チームの目的・ゴールを明確に伝える
- 役割分担や進め方を初期段階で共有する
- メンバーが自由に意見を言えるよう促す
- 雑談やアイスブレイクなど、交流のきっかけをつくる
形成期は、チームの基盤をつくるフェーズです。ここで信頼関係の土台が築けるかどうかが、次のステージへのスムーズな移行に大きく関わります。
どれくらいの期間?チームのサインを見逃さない
形成期がどれくらい続くかは、チームの規模や性質、外部環境によって異なりますが、数日〜数週間程度であることが一般的です。ただし、意識してマネジメントしないとこの段階が長引き、「なんとなく動いてるけど、本音で話せないチーム」になることもあります。
このフェーズで大切なのは、「いま、チームは形成期にいる」という認識を持つことです。そのうえで、以下のようなサインを見逃さないことが、早期の信頼構築につながります。
形成期によく見られるチームのサイン
- 会話が表面的で、雑談が少ない
- 会議で発言が少なく、誰かが引っ張っているだけ
- 「この人はどんな人だろう」という探り合いが見える
- 雰囲気は悪くないが、なんとなく遠慮がある
この段階を見極め、積極的にチームビルディングの機会を作ることが、次の「混乱期(Storming)」へのスムーズな移行に大きく関わります。
ステージ2|混乱期(Storming)
対立が表面化する理由とよくある課題
混乱期(Storming)は、形成期を経てメンバーが少しずつ本音を出し始めたことで、意見の衝突や役割の不満が表に出てくるフェーズです。ここはチームにとって最初の本格的な“壁” とも言えます。
この段階では、以下のような現象がよく起こります:
- 意見のぶつかり合いや、価値観の違いによる摩擦
- リーダーシップのスタイルに対する不満
- 役割分担に対する納得感の低下
- チームの方向性に対する疑問や異論
特に「誰がリーダーシップを取るのか」「どの方法で進めるのが最適か」など、チームの基盤に関わる重要な論点で対立が発生しやすくなります。
また、メンバーの間で“仲良し”と“仕事のやり方の違い”がぶつかる場面も見られます。
よくある課題
- 会議が長引く、結論が出ない
- 感情的な対立が発生し、気まずい空気になる
- “一部の人だけが動く”ようなアンバランスな稼働状態
- メンバーのモチベーションが下がる
一見、ネガティブに見えるこのフェーズですが、実はこの対立をどう乗り越えるかが、チームが本当の意味で成熟するかどうかの分岐点になります。
乗り越えるためにリーダーができること
混乱期は、チームが成長するために避けて通れない「通過点」です。
この時期にリーダーが果たすべき役割は、対立や摩擦を“健全な対話”に変えるファシリテーターになることです。
以下のようなアクションが有効です。
リーダーが実践したいアクション
- 衝突を否定せず、オープンに対話する場をつくる
→「これは成長に必要なプロセス」とメンバーに認識してもらうことが大切です。 - 個々の意見を引き出す質問を投げかける
→ 例:「このやり方に違和感があるとしたら、どこだと思いますか?」 - 感情と論点を切り分けて整理する
→ 感情に流されず、「事実」と「意見」を明確に区別します。 - 一人ひとりの立場を尊重する
→ 誰かを正解・不正解と決めつけず、共通点を見出す姿勢を保ちます。
また、この時期に「コンフリクトを避けてしまう」と、チームが停滞してしまう可能性があります。
あえて議論を避けるのではなく、建設的に向き合う姿勢を育てることが、統一期への鍵になります。
ステージ3|統一期(Norming)
信頼と協調が生まれるフェーズの作り方
混乱期を乗り越えると、チームは次第に信頼関係と協調性を築きはじめる「統一期」に入ります。
このフェーズでは、チームの中に共通ルールや文化が生まれ、メンバー同士が自発的に動き始めるのが特徴です。
この段階で見られるチームの特徴
- メンバー間で助け合いが増える
- 役割分担が自然に機能しはじめる
- 意見の違いがあっても冷静に調整できる
- チームとしてのアイデンティティや一体感が強まる
この時期は「チームらしさ」が育まれるフェーズであり、まさに “個の集合”から“協働する組織”への転換点 です。
ただし、ここで油断してしまうと、せっかくできたバランスが崩れてしまう可能性もあります。
リーダーはこのフェーズでも引き続き“空気作り”に気を配る必要があります。
リーダーが意識すべきポイント
- 成功体験をチームで共有する機会をつくる
→ 例:「〇〇さんのこのアイデアが役立ったよね」など、ポジティブな振り返り - 明文化されていないルールを言語化・整理する
→ 無意識のうちに生まれた“なんとなくのやり方”を、チームで合意形成する - 新たなメンバーが加わったときのフォロー体制を整える
→ 統一した文化を守るための「オンボーディング」も重要です
統一期は、いわば「安定期」。ここをしっかり築けるかが、次のステージ=成果フェーズである機能期への橋渡しになります。
ステージ4|機能期(Performing)
成果が生まれる組織への移行
統一期を経て、チームが真に機能し始めるのがこの機能期(Performing)です。この段階では、メンバーがそれぞれの役割を理解し、主体的に動きながら高いパフォーマンスを発揮できるようになります。
このフェーズの特徴
- チーム全体で共通目標に向けて集中できている
- メンバー間の信頼が厚く、自己管理・相互支援が自然に行われている
- 外部環境の変化やトラブルにも柔軟に対応できる
- リーダーの関与は最小限でもチームが機能する
まさに「1+1が3以上になる」状態で、チームとしての創造性・効率性が最大化されるフェーズです。
リーダーの役割もこの時期には変化します。強く主導するというより、支援者・促進者の立場にシフトするのが理想です。
機能期のリーダーが心がけるべきこと
- 成果をチームでしっかりと“喜ぶ”文化を育てる
- 必要な場面でのみサポートを提供する(過干渉はNG)
- 次なるチャレンジや改善提案を促す
- 個人の成長にも目を向ける評価・フィードバックを行う
この段階では、チームの成果だけでなく、個人がどれだけ成長し続けられるかにも目を向けることで、より持続可能で強い組織へと進化します。
ステージ5|散会期(Adjourning)
終わりを前向きに活かす「振り返り」の視点
タックマンモデルの最終ステージ「散会期」は、チームがその役割を終え、解散や離脱を迎える段階です。
このステージは、単なる“終わり”ではなく、次のスタートに向けた重要なフェーズでもあります。
散会期に見られる特徴
- プロジェクトや業務の完了
- メンバーが別のチームへ異動・解散
- 一時的なチームの任務終了
この段階では、達成感や満足感と同時に、喪失感や不安感が出てくることもあります。
「もっと一緒にやりたかった」「次はどうなるんだろう」という声が出るのも自然なことです。
この時期、リーダーが意識すべき最大のテーマは「振り返りと承認」です。
リーダーができること
- チームの成果やプロセスをしっかりと振り返る
→ 実施例:簡易レポート、振り返りミーティング、1on1など - メンバー一人ひとりの貢献を認め、言葉にして伝える
→ 「あなたの〇〇がチームにとって大きかった」という具体的なフィードバック - 次の成長へのつながりを意識する
→ 例:「今回の経験を活かして、次のプロジェクトでは〇〇に挑戦してみよう」
また、チーム全体としても、「この経験から何を学べたのか?」を共有することで、個人の学びと組織のナレッジ蓄積にもつながります。
チームの心理的安全性については「心理的安全性=ぬるま湯」ではない!成長する組織に必要な環境とは?」も参考になります。
活用事例に学ぶ!タックマンモデルの実践と効果
プロジェクトチームでの実践例
タックマンモデルは、理論として知っているだけでなく、実際のプロジェクトマネジメントの現場で「使える」ツールとしても活用されています。
特に、期間限定のチームや、部署をまたいだクロスファンクショナルなプロジェクトにおいて、その有用性が発揮されます。
実践例:IT企業でのシステム開発プロジェクト
あるIT企業では、複数部署からメンバーを集めたシステム開発チームを立ち上げました。
以下のような流れでタックマンモデルを活用しています:
- 形成期: 初回キックオフ時に全員の自己紹介とプロジェクトのビジョン共有を行い、「目的の共通理解」を重視
- 混乱期: 要件定義で部門間の優先順位にズレが生じたが、定例会議で各部門のニーズを丁寧にヒアリングしながら調整
- 統一期: 共通のプロジェクトルール(Slackの使い方、レビューの頻度など)を設け、徐々に役割とペースが安定
- 機能期: チーム内での問題解決や提案が自主的に行われ、マネージャーはほぼファシリテーターに徹する形に
- 散会期: リリース完了後に「振り返りワークショップ」を実施。改善点や成功体験をドキュメント化し、次のPJに共有
このように、各フェーズごとに「どんな状態か」「どのようなアクションが必要か」を意識しながら進めることで、スムーズで高成果なチーム運営が可能になります。
また、プロジェクトが短期でも、タックマンモデルをあらかじめ意識して設計することで、問題発生時にも「いま混乱期にいるな」と冷静に状況判断できるという利点もあります。
教育・看護など業種別での活用シーン
タックマンモデルは、ビジネス現場だけでなく、教育や医療などの“人間関係と協働”が重要な分野でも広く活用されています。
各業種ならではのチームの特性に応じて、ステージごとの対応が求められます。
教育現場での活用:教員チームや学級運営
学校では、教職員同士のプロジェクトや、学級運営においてもタックマンモデルが応用されています。
- 形成期: 新学年のスタート時、教師間・生徒間の関係性はまだ浅く、環境づくりが重要
- 混乱期: 生徒同士のトラブル、保護者対応の方針の違いなど、意見のぶつかりが生じる
- 統一期: 共通ルールが定着し、学級としての一体感や教員間のチームワークが育つ
- 機能期: 生徒が自主的に活動でき、教師も生徒も役割を理解し支え合う
- 散会期: 学期末、卒業などのタイミングで振り返りと成長の実感を共有
特に学級運営では、生徒の状態をこのモデルに当てはめて観察することで、早期の介入や支援に役立つという声もあります。
医療・看護の現場での活用:多職種連携チーム
看護や医療の現場では、医師・看護師・リハビリ職など異なる専門性を持つ職種間での連携が必要不可欠です。
ここでもタックマンモデルが、チーム内の信頼形成と課題解決のフレームワークとして利用されています。
- 形成期: 新しいチームが構成された直後は、職種間の壁があり連携が不安定
- 混乱期: 意見や価値観の違いから、患者ケアの優先順位に対する認識のずれが生じる
- 統一期: 互いの専門性を理解し始め、ケア方針の共有がスムーズになる
- 機能期: 連携が円滑になり、患者中心のケアが実現される
- 散会期: 患者の退院などを機にチームが解散し、ケアの成果を振り返る
こうした分野では、タックマンモデルによって「対立を避けるのではなく、活用する」姿勢を育てることができ、チーム医療の質向上にもつながっています。
新人チームでの導入事例と効果
新入社員や新卒メンバーで構成される「新人チーム」は、まさにタックマンモデルが最も効果を発揮しやすい場面の一つです。
なぜなら、経験や人間関係がゼロに近い状態からスタートするため、チームが形成・成長していくプロセスが明確に観察できるからです。
事例:大手メーカーの新人研修プログラム
ある大手メーカーでは、タックマンモデルを取り入れた新人研修プロジェクトを設計。約3ヶ月にわたるチーム型課題(商品企画、課題解決ワークショップなど)を通じて、チームビルディングとリーダーシップ育成の両面を狙っています。
プロセスの一例
- 形成期: 研修初期、メンバーは遠慮がちで積極的な発言が少ない状態。チームルールの策定やアイスブレイクで関係性の土台を構築。
- 混乱期: 課題の進め方を巡って意見が割れ、議論が白熱。運営側はあえて介入せず、自分たちで調整する機会を与える。
- 統一期: 少しずつ意見のすり合わせが進み、役割分担や情報共有が安定してくる。
- 機能期: 発表や成果物の作成フェーズでは、メンバーが自発的に動き始め、強い一体感と集中力が見られる。
- 散会期: 発表会・修了式で他チームとの振り返りを行い、互いの成長を実感し合う時間に。
実際の効果
- チームでの対話スキルや合意形成力が向上
- ステージごとの「感情の揺れ」を通じて、他者との関わり方を学ぶ
- 各自が自分の役割や得意分野に気づく機会に
- その後の部署配属後にも「今うちのチーム、混乱期だな」と冷静に判断する力が身についたという声も
このように、新人育成の段階からタックマンモデルを導入することで、単なる研修を「実践的なチーム経験」に昇華させることができるのです。
チームビルディングの実践については「チームビルディングとは?職場での意味・やり方・成功のコツまで解説」での具体例も参考にしてください。
注意点と限界|タックマンモデルは万能ではない?
短期チームやリモート環境での課題
タックマンモデルは非常に汎用性の高い理論ですが、すべてのチームや状況に完璧に当てはまるわけではありません。
特に、短期間で成果を求められるチームやリモートワーク中心のチームでは、いくつかの課題が浮かび上がります。
1. 時間的制約が成長プロセスを圧迫する
タックマンモデルは、「段階的な成長」を前提としています。しかし、短期プロジェクトではチームが十分にステージを経る前に終了してしまうことも少なくありません。
- 混乱期に入る前に終わってしまう
- 信頼関係ができる前に解散
- 統一期以降の効果が得られにくい
そのため、特に短期プロジェクトでは最初からある程度のルール整備やチーム内合意を作っておく必要があります。
2. リモート環境での“感情の把握”が難しい
オンライン中心のチームでは、顔が見えない・雑談がしづらい・空気感がつかめないなどの理由で、ステージの移行に時間がかかったり、混乱期に気づきにくい傾向があります。
リモート特有の課題
- 表情や空気感を感じ取りにくく、衝突の火種を見逃す
- 雑談やアイスブレイクが意図的に設計されていない
- 対面よりも“無言の不満”が積もりやすい
こうした状況に対応するためには、ステージごとに必要なコミュニケーションを“明文化して仕組みに落とし込む”ことが有効です。
補足:短期・リモートでもモデルは応用可能
これらの課題を理解した上で、リーダーが意図的に設計すれば、短期・リモートでもタックマンモデルは十分活用できます。
- 初期にチームの状態を共有し、どのフェーズを意識しているか明示する
- 定例MTGの中に「最近どう感じてる?」といった感情確認の時間を設ける
- 終了時には簡単でも振り返りを行い、次の活動につなげる
モデルに対する批判とその背景
タックマンモデルは長年にわたり多くの現場で活用されてきましたが、すべての専門家や実務家が無条件で受け入れているわけではありません。一部では、その適用範囲や前提条件に対して批判的な意見もあります。
1. ステージの進行が「直線的すぎる」という指摘
モデルでは、チームが形成 → 混乱 → 統一 → 機能 → 散会という順序で進んでいくことを前提としています。しかし、実際の現場では以下のような例も多く見られます。
- 機能期に入った後に再び混乱が起こる(例:メンバー変更)
- ステージをスキップするチームも存在する
- 統一期と機能期が明確に分かれず、曖昧に混在する
このように、「常に段階的に成長するとは限らない」という現実とのズレを指摘する声があります。
2. 個人差や文化の違いが考慮されていない
タックマンモデルは、主にアメリカの職場文化を前提に開発されたため、以下のような個人や文化の多様性に十分対応していないという課題もあります。
- 国や組織文化によって“対立”の捉え方が異なる
- ハイコンテクスト文化(日本など)では、混乱期が表面化しにくい
- メンバーの性格や経験によって、同じステージでも状態が大きく異なる
そのため、画一的なフレームワークとしてではなく、“対話の起点”として柔軟に使うことが重要だとされています。
3. 実証研究が少ないという学術的な批判
心理学や組織行動論の一部では、タックマンモデルについて「実証的裏付けが弱い」という批判も存在します。つまり、多くの現場で実感ベースでは使われているものの、「科学的にそのステージ構成が正しいか?」という点については、十分に検証されているとは言えないという意見です。
こうした批判を踏まえても、タックマンモデルは「完全な正解ではなく、チームを観察し、話し合うためのツール」として位置づけることで、今なお有効に使い続けることができます。
他理論との違い(GRPI、心理的安全性)
タックマンモデルはチーム発展の“流れ”に注目したフレームワークですが、他にもチームマネジメントや組織開発に役立つ理論は多数存在します。ここでは、特によく比較される2つの理論と、タックマンモデルの違いを整理します。
GRPIモデルとの違い
GRPIモデルは、「目標(Goals)・役割(Roles)・プロセス(Processes)・人間関係(Interpersonal)」の4要素でチームの機能を分析するフレームワークです。
| 比較軸 | タックマンモデル | GRPIモデル |
|---|---|---|
| アプローチ | 成長プロセスを段階的に捉える | チームの構造と要因に焦点を当てる |
| 特徴 | チームの“状態変化”に注目 | チームの“構成要素”に注目 |
| 活用場面 | チームの発展段階を見極めたいとき | 現在の課題の要因を分析したいとき |
GRPIモデルは、特定の課題が「目標の不一致なのか、役割の曖昧さなのか」を明らかにするのに適しており、タックマンモデルの補完的ツールとして併用されることも多いです。
心理的安全性との違い
心理的安全性(Psychological Safety) は、Googleの研究などでも注目された理論で、「チーム内で自分らしく発言・行動できる感覚」を指します。
タックマンモデルと心理的安全性は、視点が異なります:
- タックマンモデル: チームの発展段階と、起こりやすい状態変化を説明
- 心理的安全性: チームの“今”の雰囲気や関係性の質を測る指標
たとえば、混乱期では心理的安全性が低下しがちですが、そこでリーダーが支援することで、次の統一期へと進みやすくなる…といった関係性が考えられます。
結論として、タックマンモデルは 「時間軸の中で変化するチームの姿を捉える理論」であり、GRPIや心理的安全性などの“状態分析系”の理論と組み合わせることで、より深いチーム理解と支援が可能になります。
今のチームはどこ?5つの質問で診断!
自分たちのチームが今どのステージにあるか、以下のチェックリストで確認してみましょう。
該当する項目が最も多いステージが、いまのチームの状態に近いと考えられます。
| ステージ | チェック項目(当てはまるものに✔) |
|---|---|
| 形成期(Forming) | □ 発言が少なく、様子見の空気がある □ メンバー間の関係性がまだ浅い □ 目的や役割が曖昧に感じる □ 指示待ちの姿勢が多い |
| 混乱期(Storming) | □ 意見がぶつかることが多い □ 話し合いが進みにくい/空気が重い □ チーム内で不満や戸惑いが見られる □ 感情的なやり取りが増えている |
| 統一期(Norming) | □ メンバー同士で自然に助け合っている □ 会話にポジティブさや安心感がある □ ルールや進め方が定着してきた □ チーム内で感謝の言葉が増えた |
| 機能期(Performing) | □ 自主的な動きが多く、成果が出ている □ トラブルにも柔軟に対応できている □ ミーティングが短時間で建設的 □ リーダーが介入しなくても回っている |
| 散会期(Adjourning) | □ チームの目的が達成された □ 振り返りや成果共有の機会がある □ メンバーに寂しさや感謝の声がある □ 次の活動への動きが始まっている |
使い方のポイント
- ひとりでチェックするもよし、チーム全体でワークとしてやるもよし!
- 「複数ステージに当てはまる…」という場合もOK。その場合は、移行期にある可能性を考えてみましょう。
このチェックリストは、“今”を見つめ直すきっかけとして使えるだけでなく、対話を生む入り口にもなります。
まとめ|チームの成長段階を理解し、より良い関係構築と成果につなげよう
チームがうまくいかないと感じたとき、私たちはつい「相性が悪いのかな」「やる気がないのかも」と個人の問題に目を向けてしまいがちです。
しかし、タックマンモデルのようにチームの発展段階を“プロセス”としてとらえる視点があれば、課題の本質がもっとクリアに見えてきます。
- チームは段階を経て成熟していくもの
- 混乱や対立も、成長に必要な通過点
- 各ステージに応じたマネジメントや関わり方がある
このような認識を持つだけでも、リーダーとして、メンバーとして、より建設的にチームと向き合うことができるようになります。
また、今回ご紹介したように、教育・看護・新人研修・プロジェクトチームなど、さまざまな現場でタックマンモデルは活用されています。
一人ひとりが「いま、私たちはどのフェーズにいるのか?」と問い直すことが、より良い関係性と成果づくりの第一歩になるでしょう。
ぜひ、この記事を参考に、あなたのチームでもタックマンモデルを“会話の土台”として活用してみてください。