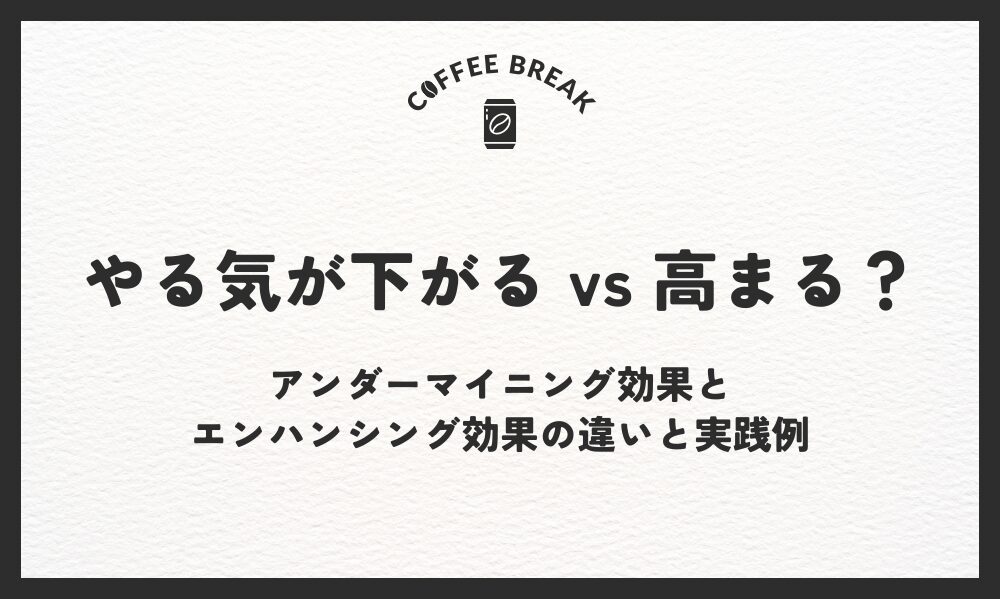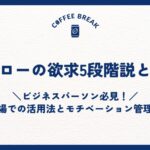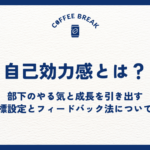目次
アンダーマイニング効果とは
アンダーマイニング効果の定義
アンダーマイニング効果(Undermining Effect)とは、ある行動に対して外部からの報酬や評価が与えられることによって、もともとその行動を支えていた内発的な動機づけが損なわれ、結果として意欲やモチベーションが低下してしまう現象です。
この効果は、1970年代に心理学者エドワード・デシによって提唱されたもので、以降、多くの実験や研究で確認されてきました。たとえば、自由に遊んでいた子どもが、報酬を与えられた途端に興味を失うなど、私たちの身近な場面でもその影響が見られます。
心理学における背景と理論
アンダーマイニング効果の理解には、自己決定理論という心理学の枠組みが欠かせません。動機づけには「外発的動機づけ」と「内発的動機づけ」の2種類があります。
外発的動機づけとは
外発的動機づけは、報酬や賞罰といった外部の要因によって行動することです。短期的な効果はありますが、継続性や主体性には課題があります。
内発的動機づけとは
一方で内発的動機づけは、「楽しいから」「知りたいから」といった内側から生まれる動機です。創造性や自発性が高まりやすい一方で、外部の介入によって損なわれやすい特徴もあります。
内発的動機を高める方法について詳しく知りたい方は「内発的動機とは?外発的動機との違いやビジネスでの活かし方を解説」もご覧ください。
アンダーマイニング効果が起こる原因
報酬が目的になる
もともと「楽しい」「興味がある」から取り組んでいた行動も、そこに報酬が加わることで、目的意識が変化することがあります。行動の原動力が「報酬を得るため」にすり替わると、報酬がない場面ではモチベーションが生まれにくくなります。行動の意味が外から与えられるようになり、主体性が薄れてしまうのです。
他者からの評価やプレッシャー
人は周囲からの期待や評価に応えようとする傾向がありますが、それが過度になると、自分の意志ではなく「他人の目を意識して行動する」ようになります。これは本人の自主性や創造性を損ない、やる気が“義務感”に変わってしまい、モチベーションの低下につながる要因となります。
やらされ感と自由の喪失
自分で選んで始めたことでも、細かな指示や管理が加わると「やらされている」と感じるようになります。こうした状況では、本来感じていた達成感や楽しさが薄れ、義務感やストレスが前面に出てきます。人は自由を奪われると、行動への熱意を失いやすくなるのです。
具体例で理解するアンダーマイニング効果
教育現場でのケース
教育の場では、報酬制度や点数による評価が学習意欲に与える影響が顕著に現れます。たとえば「100点を取ればご褒美」というルールは、一時的なやる気を引き出せますが、それが習慣化すると「報酬がなければ勉強しない」という状態になり、知識への興味や探求心といった内発的動機が損なわれてしまいます。
ビジネスシーンでの例
現場では、報酬制度や評価体系が社員の行動スタイルに強い影響を与えます。たとえば営業職では、数字ばかりが重視されることで、顧客との関係構築より成果を優先する行動が定着しがちです。このような制度設計が続くと、仕事の本来の価値が見えにくくなり、組織全体の創造力や柔軟性が損なわれる恐れがあります。
趣味・プライベートに与える影響
趣味やプライベートな活動でも、アンダーマイニング効果は起こります。SNSでの“いいね”やフォロワー数など、他者からの評価を意識しすぎると、純粋な楽しみだった活動がプレッシャーに変わり、義務感やストレスを感じるようになります。こうした状況では、活動自体から離れてしまうケースも少なくありません。
アンダーマイニング効果が及ぼす影響
モチベーションの低下
報酬に依存した行動は、内発的な興味や関心を徐々に奪い取っていきます。その結果として、報酬がないときには「やる理由がない」と感じてしまい、意欲が続かなくなります。このように、動機の外部化は継続的な行動を阻害し、やる気が持続しない状態を引き起こす原因となります。
創造性や自発性の阻害
評価や報酬に意識が向きすぎると、人は“失敗できない”という心理状態に陥り、チャレンジ精神を失いやすくなります。その結果、斬新な発想や主体的な行動が抑えられ、決まりきった枠の中でしか動けなくなってしまうことがあります。創造性には、自由と安心感が不可欠なのです。
人間関係やチームへの悪影響
報酬や評価が個人の成果に偏ると、チーム内の協力よりも競争が優先されるようになります。このような環境では、信頼関係が築きにくくなり、情報共有や助け合いが減少し、組織のパフォーマンスも低下します。長期的には、職場の雰囲気や人間関係に悪影響を及ぼすこともあります。
マズローの欲求5段階説とのつながりにも注目
アンダーマイニング効果は、人の承認欲求や自己実現欲求を損なうリスクがあります。この点で、マズローの「欲求5段階説」との関連性も見逃せません。人間の根源的な欲求とモチベーション理論についてより深く知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。
アンダーマイニング効果を防ぐには
外発的報酬の与え方を見直す
報酬が必ずしも悪いわけではありません。重要なのは「与え方」と「タイミング」です。行動前に与える報酬は内発的動機を奪いやすいですが、行動後に感謝や承認の意味で渡される報酬は、やる気を後押しすることもあります。報酬を「目的」にせず「結果への敬意」として扱うことで、モチベーションを維持しやすくなります。
「ほめ方」とフィードバックの工夫
「すごいね!」という結果重視のほめ方は、時にプレッシャーになります。効果的なのは、努力や工夫、取り組みの過程に焦点をあてた言葉がけです。また、本人の気持ちを尊重し、問いかけを交えたフィードバックをすることで、相手の主体性を引き出し、内発的動機づけを高めることができます。
自己効力感を高める方法については「自己効力感とは?部下のやる気と成長を引き出す目標設定とフィードバック法」の記事も参考になります。
自己決定感を尊重する環境づくり
アンダーマイニング効果を防ぐには、本人が「自分の意思で決めた」と感じられる状況をつくることが大切です。教育や職場では、選択肢を与えたり、進め方の裁量を持たせることで、その人の主体性が引き出されやすくなります。制度やコミュニケーションの設計が、内発的動機を支える土台となります。
エンハンシング効果とは
エンハンシング効果とは、報酬や評価といった外的要因が、逆に内発的なモチベーションを高める方向に働く心理効果のことです。これは、アンダーマイニング効果とは対照的な現象として知られています。
アンダーマイニング効果との違い
アンダーマイニング効果が外発的報酬によって内発的動機を損なう現象であるのに対し、エンハンシング効果はその逆です。報酬や評価が本人の価値観や努力と調和して与えられたとき、内発的なやる気を高めることがあります。この違いを理解することで、効果的なモチベーション支援が可能になります。
| 項目 | アンダーマイニング効果 | エンハンシング効果 |
|---|---|---|
| 結果 | モチベーションの低下 | モチベーションの向上 |
| 原因 | 外発的報酬が主目的になる | 報酬が本人の価値観と一致する |
| 影響 | 内発的動機が弱まり行動が継続しづらくなる | 内発的動機が強まり自発的に行動を継続できる |
| 典型例 | 成績アップのためだけのご褒美制度 | 努力を認めるフィードバックやサプライズ報酬 |
| 注意点 | 与えすぎ、タイミングの悪さ、義務感 | 適切なタイミングと自然な承認が鍵 |
モチベーションを高めるための活用法
エンハンシング効果を活用するには、外発的報酬を「行動の補完」として機能させることが重要です。努力を認めたり、相手の自信が揺らいでいる場面で前向きな声かけをすることで、内発的動機を刺激できます。報酬やフィードバックは、相手の価値観やタイミングに合った形で伝えることが鍵です。
努力を認める
「がんばってたね」「工夫していたね」といったプロセスへの称賛は、内発的動機を育てます。
タイミングや場面を考慮した声かけ
フィードバックは行動直後や自信が揺らいでいるときに与えると効果的。自然な形での声かけが大切です。
逆効果になる「ほめ方」とは
一見ポジティブに見えるほめ言葉でも、結果偏重や比較ベースの評価は、相手にプレッシャーを与えたり、不安感を強めることがあります。「すごいね、あの子より上手だった!」といった言い回しは、自尊感情や内発的動機を損なう可能性があるため、注意が必要です。評価はあくまで本人の努力に焦点を当てることが大切です。
まとめ|アンダーマイニング効果の理解と対策が生むポジティブな変化
アンダーマイニング効果は、短期的な成果を求める中で見落とされがちな心理的落とし穴です。報酬や評価の設計やコミュニケーションの取り方ひとつで、人のやる気や成長に大きな差が生まれます。
逆に、エンハンシング効果を意識すれば、外発的刺激を味方にしてモチベーションや創造性を高めることが可能です。
- 行動の目的が「報酬」にならないよう注意する
- 努力やプロセスに目を向けた評価を行う
- 自己決定感を尊重する関わり方を意識する
このような考え方を取り入れることで、個人の成長、チームの一体感、教育の質など、さまざまな面にポジティブな変化をもたらすことができます。
「やらされる」から「やりたい」へ――
その変化を導くのは、私たち自身の接し方と環境づくりなのです。