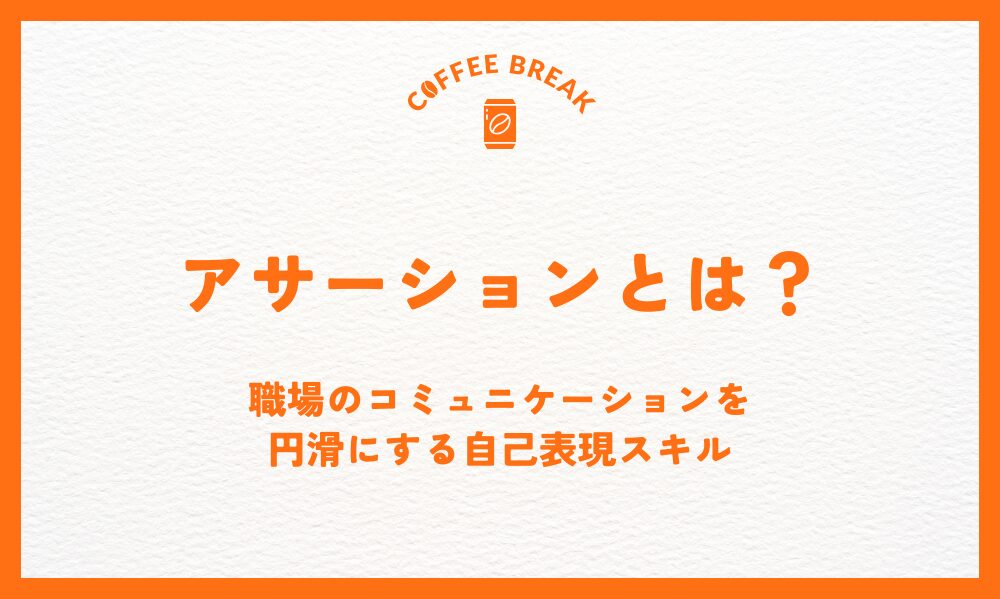自分の意見をしっかり伝えたいけれど、相手を傷つけたくない。そんなジレンマを感じたことはありませんか?ビジネスシーンでは、自分の考えを適切に表現しつつ、良好な人間関係を維持することが大切です。そのバランスを取るために有効なコミュニケーションスキルが「アサーション」です。
アサーションとは、「自分も相手も大切にしながら、自分の意見や気持ちを誠実に伝えるコミュニケーション方法」のことを指します。このスキルはビジネスの場だけでなく、プライベートの人間関係においても非常に役立ちます。
近年、ハラスメント対策や働き方改革、テレワークの普及により、アサーションへの注目が高まっています。本記事では、アサーションの基本から実践方法まで、わかりやすく解説します。
目次
アサーションとは
アサーション(assertion)は、英語で「主張」「断言」「自己主張」などの意味を持つ言葉です。日本語では「自他尊重のコミュニケーション」とも呼ばれています。
つまり、アサーションとは「相手も自分も大切にする自己表現」のことを言います。これは単なる自己主張ではなく、互いを尊重し合うことが前提です。
アサーションでは、自分の気持ちや意見をはっきりと伝えながらも、相手を否定したり傷つけたりしないよう配慮します。また、自分の意見を抑えて相手に合わせるのでもありません。相互理解を深めながら、建設的な対話を目指すのがアサーションの本質です。
アサーションの起源
アサーションは1950年代にアメリカで生まれた概念です。当初は、対人不安や社会的スキルの欠如に悩む人々を対象とした行動療法のひとつとして始まりました。
その後、1960年代の公民権運動と女性解放運動の流れの中で発展し、「自分の権利を主張すること」の重要性が広く認識されるようになりました。自分の意見をしっかり持ちながらも、他者を尊重する姿勢は、社会的弱者の権利獲得運動とも結びついていったのです。
日本では1980年代に平木典子氏によってアサーションが紹介され、「自己表現」や「自己主張」の健全な在り方として注目されるようになりました。現在では、ビジネスの場や医療、教育など、さまざまな分野でアサーショントレーニングが実施されています。
アサーションが注目される背景
近年、日本でアサーションが注目されている背景には、いくつかの社会的な変化があります。
ハラスメントへの意識の高まり
日本では、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントに対する社会的関心が高まっており、2020年6月にはパワハラ防止法も施行されました。
厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、職場でパワハラを受けた人の多くが「上司と部下のコミュニケーションが少ない/ない」と回答しています。この背景には、意見を適切に伝えられなかったり、コミュニケーションの齟齬や誤解が生じていたりする状況があると考えられます。
パワハラ防止法のポイント
- 2020年6月から大企業、2022年4月から中小企業に適用
- 事業主に対して、パワハラ防止のための雇用管理上の措置が義務付け
- 適切なコミュニケーションスキルの習得が重視される
アサーションを実践することで、相手を尊重しつつ自分の意見も率直に伝えられるようになるため、ハラスメントのリスク軽減が期待できます。
テレワークの増加
コロナ禍をきっかけに、多くの企業でテレワークが導入されました。対面でのコミュニケーションが減少し、テキストベースのやり取りが増えたことで、新たなコミュニケーション課題も生まれています。
テキストコミュニケーションでは、表情や声のトーンなどの非言語情報が伝わりにくいため、誤解が生じやすくなります。また、リモートワーク環境では「言いにくいことを伝える」ハードルが上がりがちです。
こうした背景から、「相手に配慮しながらも明確に自分の意見を伝える」アサーションのスキルが、より一層求められるようになっています。
メンタルヘルス対策
職場のメンタルヘルス問題も深刻化しています。厚生労働省の調査によると、労働者の約6割が「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスがある」と回答しています。
自分の気持ちを適切に表現できないことで、ストレスが溜まり、メンタルヘルスの悪化につながるケースも少なくありません。アサーションを身につけることで、適切に自己表現し、ストレスを軽減することができます。

アサーションの効果
アサーションを身につけることで、どのような効果が期待できるのでしょうか。ここでは主な効果を3つ紹介します。
対等な意見交換ができる
アサーションを身につけると、相手の立場や役職に関わらず、対等な立場で意見交換ができるようになります。
特に、取引先や上司など目上の相手に対しても、必要なことを適切に伝えられるようになります。単に「言いたいことを言う」のではなく、相手の立場を尊重しながらも自分の意見をしっかり伝えることで、建設的な対話が可能になります。
人間関係が円滑化する
アサーティブなコミュニケーションを心がけることで、周囲との信頼関係が深まり、人間関係が円滑になります。
自分の気持ちを正直に伝えつつも相手への配慮を忘れないことで、互いの理解が深まります。また、誤解や不満が溜まることが少なくなるため、長期的な人間関係を構築するのに役立ちます。
相手を不快にさせずに断れる
「NO」と言うのが苦手な人は多いものです。しかし、自分のキャパシティを超えた依頼を受けてしまうと、結果的に相手の期待に応えられなくなってしまいます。
アサーションを身につけることで、相手を不快にさせることなく、断る勇気と技術を身につけることができます。相手の要望を尊重しつつも、自分の状況や気持ちを誠実に伝えるスキルは、ビジネスパーソンにとって非常に重要です。

アサーションでの3つのコミュニケーションスタイル
アサーションでは、コミュニケーションのスタイルを主に3つのタイプに分類します。どのタイプなのかを理解することで、自分自身のコミュニケーションスタイルを客観的に捉えることができます。
アグレッシブ(攻撃タイプ)
アグレッシブタイプは、自分の意見を強く主張し、相手の意見や感情を軽視するコミュニケーションスタイルです。
アグレッシブなコミュニケーションの特徴:
- 自分の権利や意見を最優先する
- 相手の意見を無視または軽視する
- 威圧的な態度や口調を使う
- 自分の感情をコントロールできないことがある
- 短期的には目的を達成できるが、長期的には人間関係を損なう
アニメ『ドラえもん』のキャラクターに例えると、ジャイアンがこのタイプにあたります。「お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの」という台詞が象徴的です。
アグレッシブなコミュニケーションは、一見すると自己主張ができているように見えますが、相手との信頼関係を損ない、長期的には協力を得られなくなるというデメリットがあります。
ノンアサーティブ(非主張タイプ)
ノンアサーティブタイプは、自分よりも他者を優先し、自分の意見や感情を表現しないコミュニケーションスタイルです。
ノンアサーティブなコミュニケーションの特徴:
- 自分の権利や欲求よりも相手を優先する
- 意見や感情を表現することを恐れる
- 「申し訳ない」「ごめんなさい」などの言葉を頻繁に使う
- 自己肯定感が低く、ストレスを抱えやすい
- 他者に利用されやすい
『ドラえもん』では、のび太くんがこのタイプに該当します。ジャイアンの無理な要求にも断れず、渋々従ってしまう姿が思い浮かびます。
ノンアサーティブなコミュニケーションは、表面上は円滑な人間関係が保たれているように見えますが、実際には自分の不満や不安を溜め込むことになり、最終的には心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
アサーティブ(バランスタイプ)
アサーティブタイプは、自分と相手の権利や感情を尊重し、誠実かつ率直にコミュニケーションするスタイルです。これがアサーションが目指す理想的なコミュニケーションです。
アサーティブなコミュニケーションの特徴:
- 自分の権利を守りながら相手の権利も尊重する
- 感情や意見を率直に表現する
- 冷静で穏やかな口調で話す
- Win-Winの解決策を目指す
- 長期的に良好な人間関係を構築できる
『ドラえもん』では、しずかちゃんがこのタイプに近いと言えるでしょう。相手の気持ちを尊重しつつも、自分の意見をきちんと伝える姿勢を持っています。
3つのタイプの比較
| タイプ | 自分の扱い | 相手の扱い | 結果 |
|---|---|---|---|
| アグレッシブ | 勝ち | 負け | 短期的な目標達成 |
| ノンアサーティブ | 負け | 勝ち | 不満の蓄積 |
| アサーティブ | 勝ち | 勝ち | Win-Win |
アサーションのトレーニング方法
アサーションのスキルは、生まれながらに備わっているものではなく、後天的に身につけるものです。アサーションを習得するためには、継続的なトレーニングが必要です。ここでは、代表的なアサーショントレーニングの方法を紹介します。
アサーションチェック
まずは現在の自分がどの程度アサーティブなコミュニケーションができているかを確認しましょう。以下のチェックリストを使って、自分のコミュニケーションスタイルを診断してみてください。
アサーションチェックリスト:
- 自分の考えや意見を率直に表現できる
- 相手の意見と自分の意見が異なる場合でも、自分の意見を伝えられる
- 必要なときには「NO」と言える
- 自分の気持ちや感情を適切に表現できる
- 相手を尊重しながらも自分の権利も守れる
- 批判やフィードバックを受け入れることができる
- 自分の間違いを素直に認めることができる
- 相手の表情や態度に注意を払いながら会話できる
- 感情的になりすぎずに冷静に話し合える
- 建設的な解決策を一緒に考えることができる
各項目について、「はい」なら1点、「いいえ」なら0点として、合計点を計算してみましょう。
- 8〜10点:アサーティブなコミュニケーションができています
- 5〜7点:おおむねアサーティブですが、改善の余地があります
- 0〜4点:アサーティブなコミュニケーションを意識的に学ぶと良いでしょう
DESC法
DESC法は、アサーションのプロセスを4つのステップに分解した方法です。特に「言いにくいこと」を伝える際に役立ちます。
DESC法の4つのステップ:
- D(Describe):描写する
客観的な事実を述べる - E(Express/Explain/Empathize):表現・説明・共感する
自分の気持ちや考えを「私は〜」という形で伝える - S(Specify):具体的に提案する
望ましい解決策を具体的に提案する - C(Choose):選択肢を示す
提案が受け入れられた場合と受け入れられなかった場合の結果を示す
具体例:締め切りが厳しい場合

ABCDE理論
ABCDE理論は、認知行動療法の考え方を応用したアサーショントレーニングの方法です。自分の思考パターンを見直し、より適応的な考え方に変えていくことを目指します。
ABCDE理論の5つのステップ:
- A(Activating Event):出来事
何が起きたのか? 客観的な事実 - B(Belief):信念
その出来事についてどう考えたか? - C(Consequence):結果
その考えによってどのような感情や行動が生じたか? - D(Dispute):反論
その考え方は合理的か? 別の見方はないか? - E(Effect):効果
考え方を変えることで得られる新たな結果
具体例:提案が上司に却下された場合
- A:会議で私の提案が上司に却下された
- B:「私の意見は価値がないと思われている」
- C:落ち込んで、今後意見を言うのをためらうようになった
- D:「却下されたのは私自身ではなく提案内容。改善して再提案するチャンスかもしれない」
- E:建設的なフィードバックを求め、提案を改善して再チャレンジする自信が生まれた
I(アイ)メッセージ
アイメッセージとは、「私は〜」という主語で始まるメッセージのことです。相手を非難せずに自分の気持ちを伝えることができるため、アサーションにおいて非常に重要なスキルです。
アイメッセージの特徴:
- 主語が「私」であり、自分の感情や考えを伝える
- 相手を責めず、自分の視点から状況を説明する
- 相手の行動が自分にどう影響しているかを伝える
アイメッセージとユーメッセージの比較
| ユーメッセージ(相手主語) | アイメッセージ(自分主語) |
| あなたは遅刻ばかりしている | 約束の時間に来てもらえないと、私は待ち時間を無駄にしてしまうので困ります |
| もっと早く言ってよ! | もう少し早く教えてもらえると、私も準備する時間が取れるので助かります |
| わかりにくい説明だね | 私には理解が難しいので、もう少し具体例を交えて説明してもらえませんか |
ユーメッセージは相手を責める印象を与えがちですが、アイメッセージは自分の気持ちを伝えつつも相手を尊重する姿勢を示すことができます。
アサーション権
アサーション権とは、「誰もが持っている基本的な権利」のことです。自分にも相手にもこれらの権利があることを理解し、尊重することが、アサーティブなコミュニケーションの基盤となります。
代表的なアサーション権:
- 自分の気持ち、意見、考え、信念を表現する権利
- 自分の行動とその結果に責任を持つ権利
- 「NO」と言う権利
- 要求をする権利
- 間違いをする権利
- 考えや意見を変える権利
- 「わからない」と言う権利
- 他者の問題に巻き込まれない権利
これらの権利は、自分だけでなく、相手にも同等に認められるものです。アサーション権を意識することで、自分の権利を行使すると同時に、相手の権利も尊重するバランスが取れるようになります。
言語的アサーションと非言語的アサーション
アサーションには、言葉で伝える「言語的アサーション」と、表情やジェスチャーなどで伝える「非言語的アサーション」があります。効果的なコミュニケーションのためには、両方を意識することが大切です。
言語的アサーション:
- 「私は〜」というアイメッセージを使う
- 具体的で明確な表現を心がける
- 感情を適切に言語化する
- 相手の発言を否定せず、自分の意見を付け加える
非言語的アサーション:
- 適切なアイコンタクトを取る
- 姿勢を正し、相手に向き合う
- 落ち着いた声のトーンで話す
- 表情や身振りを意識する
言語的アサーションと非言語的アサーションが一致していないと、メッセージの信頼性が低下します。例えば、「大丈夫です」と言いながら、表情は不満そうであれば、相手は混乱してしまいます。両者の一貫性を意識しましょう。
アサーションの具体例
アサーションをより理解するために、日常的に起こりうる場面での具体例を見ていきましょう。
具体例1:業務量が多すぎる場合
状況:上司から新しいプロジェクトを任されたが、現在の業務量ですでに手一杯である。
ノンアサーティブな対応:
「わかりました、頑張ります…」(内心では「無理だ」と思っている)
アグレッシブな対応:
「無理です!今でさえ忙しいのに、これ以上仕事が増えたら体が持ちません!」
アサーティブな対応:
「新しいプロジェクトをお任せいただき、ありがとうございます。現在、A案件とB案件を担当しており、納期も迫っていますので、優先順位についてご相談させていただきたいです。新プロジェクトを担当するならば、どれかの業務を移管するか、納期の調整をしていただけると助かります。」
具体例2:会議で意見を述べる場合
状況:会議で自分とは異なる意見が大勢を占めているが、重要な視点が抜け落ちていると感じている。
ノンアサーティブな対応:
(黙っている、または周りに合わせて同意する)
アグレッシブな対応:
「その案では絶対に失敗します。私の意見を聞かないと後悔しますよ。」
アサーティブな対応:
「皆さんの意見は理解できます。そのうえで、もう一つの視点を提案したいと思います。○○の観点からは、△△というリスクも考えられます。このリスクを回避するために、□□という対策も検討してはいかがでしょうか?」
具体例3:誘いを断る場合
状況:同僚から飲み会に誘われたが、その日は家族との予定がある。
ノンアサーティブな対応:
「う〜ん、ちょっと…」(はっきり断れない)または予定を変更して参加する
アグレッシブな対応:
「無理です。私にはもっと大事な予定があります。」
アサーティブな対応:
「誘っていただきありがとうございます。ぜひ参加したいのですが、その日は家族との大切な予定があるので、今回は失礼させてください。次回はぜひ参加させてください。」
アサーションに関するよくある質問
ここでは、アサーションに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
アサーションとアサーティブの違いは何ですか?
アサーションは、自分も相手も大切にする自己表現やコミュニケーション方法のことを指します。一方、アサーティブは、そのようなコミュニケーションができる状態や人の性格・行動を表す形容詞です。「アサーション」ができている状態を「アサーティブ」と表現します。
アサーティブとアグレッシブの違いは何ですか?
アサーティブは、自分と相手の両方の権利を尊重し、誠実かつ率直に自己表現するコミュニケーションスタイルです。一方、アグレッシブは、自分の権利や意見を強く主張するあまり、相手の権利や感情を軽視してしまうコミュニケーションスタイルです。どちらも自己主張はしますが、相手への配慮の有無が大きな違いです。
アサーションスキルを身につけるには、どのくらいの期間が必要ですか?
人によって異なりますが、アサーションスキルは一朝一夕で身につくものではありません。継続的な練習と実践が必要です。まずは簡単な場面から始めて、少しずつ難しい場面にチャレンジしていくと良いでしょう。3〜6ヶ月程度の継続的なトレーニングで、基本的なスキルは身につけることができます。ただし、本当に自分のものにするためには、日常的に意識して実践し続けることが大切です。
アサーションは日本の文化に合わないのではないでしょうか?
日本の文化では確かに「和を以て貴しとなす」という考え方があり、自己主張よりも協調性が重視される傾向があります。しかし、アサーションは単なる自己主張ではなく、相手を尊重しながら自分の意見を伝えるコミュニケーション方法です。むしろ、お互いを尊重するという点では、日本文化の「思いやり」の精神とも共通する部分があります。職場環境や社会の変化に伴い、適切な自己表現ができることの重要性は増しており、日本の文化に合った形でアサーションを取り入れていくことは十分に可能です。
アサーションスキルを身につけるための本やトレーニングプログラムはありますか?
日本でのアサーショントレーニングの第一人者である平木典子氏の著書『アサーション・トレーニング』や『マンガでやさしくわかるアサーション』はわかりやすく実践的です。また、各地でアサーショントレーニングのワークショップやセミナーも開催されています。企業向けの研修プログラムも増えていますので、自分に合った学習方法を選ぶとよいでしょう。オンラインでも多くの学習リソースが提供されています。
アサーションを身につけるためのポイント
最後に、アサーションを身につけるためのポイントをまとめます。
自分のコミュニケーションパターンを知る
まずは自分自身のコミュニケーションパターンを客観的に分析しましょう。日常のやり取りの中で、自分がどのような場面で非主張的になったり、攻撃的になったりするのかを観察します。
自分の反応パターンを知ることで、改善すべきポイントが明確になります。前述のアサーションチェックも活用してみてください。
小さな一歩から始める
いきなり難しい場面でアサーティブになろうとすると挫折しやすいです。まずは日常的な簡単な場面から始めましょう。
- 行きたいお店を提案する
- 映画の感想を素直に伝える
- 少し待ってほしいときに「少しお待ちください」と伝える
このような小さなことから始め、自信がついてきたら徐々に難易度を上げていきましょう。
失敗を恐れない
アサーションの実践では、うまくいかないこともあります。しかし、それは成長のプロセスの一部だと考え、失敗を恐れずにチャレンジしましょう。
失敗した場合は、なぜうまくいかなかったのかを振り返り、次回に活かすようにしましょう。完璧を目指すのではなく、少しずつ上達していくことが大切です。
ロールプレイで練習する
アサーションは実践的なスキルです。信頼できる友人や同僚と一緒にロールプレイをして練習してみましょう。実際の場面を想定して、アサーティブな対応を練習します。
フィードバックをもらうことで、自分では気づかない課題に取り組むことができます。また、ロールプレイを通じて、実際の場面での緊張感を和らげることもできます。
継続的に実践する
アサーションスキルは、一度身につけたら終わりではなく、継続的な実践が必要です。日常のさまざまな場面で意識的にアサーティブなコミュニケーションを心がけましょう。
また、定期的に自己評価を行い、改善点を見直すことも大切です。アサーションは生涯にわたって磨いていくスキルだと考えましょう。
まとめ
アサーションとは、自分も相手も大切にしながら、率直に自己表現するコミュニケーション方法です。近年のハラスメント防止やテレワークの増加、メンタルヘルス対策の観点から、ビジネスシーンでもその重要性が高まっています。
アサーションには、自分の意見を強く主張するアグレッシブ型、自分よりも相手を優先するノンアサーティブ型、そして自他ともに尊重するアサーティブ型の3つのコミュニケーションスタイルがあります。アサーションが目指すのは、バランスの取れたアサーティブなコミュニケーションです。
アサーションを身につけるためには、DESC法やABCDE理論、アイメッセージといったトレーニング方法があります。また、アサーション権を理解し、言語的・非言語的なアサーションを意識することも大切です。
アサーションスキルは一朝一夕で身につくものではありませんが、小さな一歩から始め、継続的に実践することで徐々に上達していきます。失敗を恐れず、日常のさまざまな場面でアサーティブなコミュニケーションを心がけましょう。
アサーティブなコミュニケーションが増えれば、職場の人間関係は円滑になり、一人ひとりが生き生きと働ける環境が作られていくでしょう。アサーションは、ビジネスパーソンにとって必須のスキルの一つと言えます。