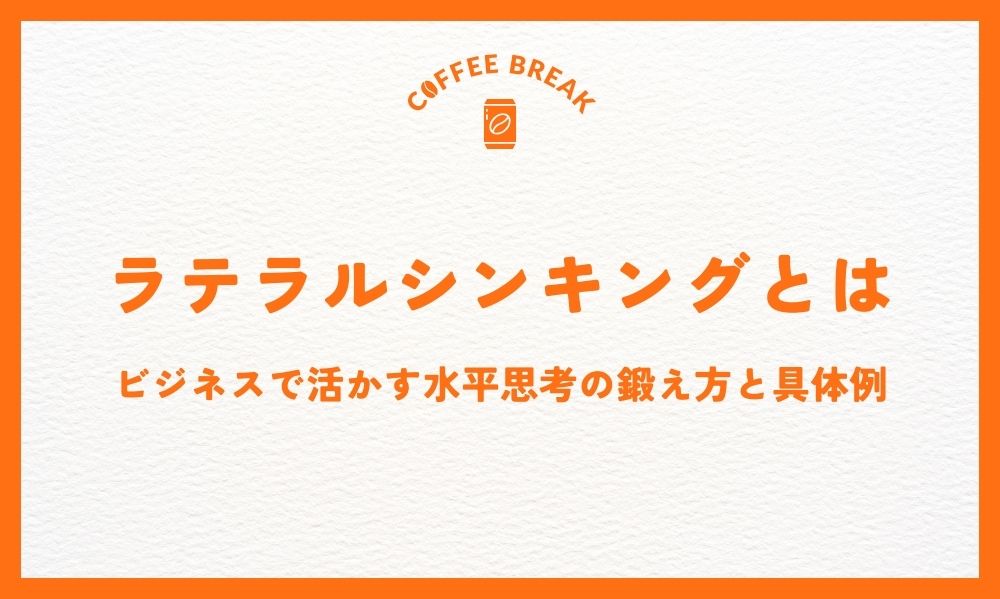変化が激しく予測不能な時代において、従来の常識や固定観念にとらわれない思考法が注目されています。その中でも「ラテラルシンキング(水平思考)」は、新たな発想や革新的なアイデアを生み出すための重要な思考法として多くのビジネスパーソンから関心を集めています。本記事では、ラテラルシンキングの基本概念から具体的な活用方法、効果的な鍛え方までを詳しく解説します。ビジネスシーンで活かせる例題も紹介しますので、創造的な問題解決力を高めたい方はぜひ参考にしてください。
目次
1. ラテラルシンキング(水平思考)とは何か
ラテラルシンキングは、1967年にマルタ出身の心理学者エドワード・デ・ボノ博士によって提唱された思考法です。従来の垂直的・直線的な思考ではなく、水平方向に発想を広げていく思考プロセスを指します。つまり、既存の枠組みや常識から離れ、多角的な視点で新しい発想やアイデアを生み出す思考法なのです。
1-1. ラテラルシンキングの意味
「ラテラル」(lateral)という言葉は英語で「横方向の」「側面の」という意味を持っています。「シンキング」(thinking)は「思考」を意味します。つまり、ラテラルシンキングとは横方向に思考を広げていくことを表しています。
通常、私たちは一つの問題に対して最も論理的で効率的な解決策を求める傾向があります。これは「垂直思考」と呼ばれ、一点に向かって掘り下げていく思考法です。一方、ラテラルシンキングでは問題を多角的に捉え、常識や前提を疑い、意外な発想や視点から解決策を見つけ出します。
1-2. 水平思考について
ラテラルシンキングは日本語では「水平思考」と訳されることが多いです。これは、思考の方向性が水平方向に広がっていくイメージからきています。水平思考では、一つの正解だけを求めるのではなく、様々な可能性や選択肢を探ることが重視されます。
水平思考の特徴は以下のとおりです:
- 既存の考え方や常識を疑う
- 多角的な視点から問題を捉える
- 創造的で革新的なアイデアを生み出す
- 「なぜそうなのか」という問いを重視する
- 偶然性や直感を大切にする
1-3. 提唱者エドワード・デ・ボノ博士について
エドワード・デ・ボノ博士は1933年にマルタで生まれ、オックスフォード大学で医学と心理学を学びました。彼は創造的思考法の研究者として世界的に知られ、「シックス・シンキング・ハット」など多くの思考法を開発しました。
デ・ボノ博士は「創造性は技術であり、訓練によって習得できる」という考え方を広め、その思想は現代のビジネス教育や問題解決手法に大きな影響を与えています。
2. ラテラルシンキングと他の思考法の違い
ラテラルシンキングの特徴をより明確に理解するために、他の代表的な思考法との違いを見ていきましょう。
2-1. ロジカルシンキング(論理的思考)との違い
ロジカルシンキングは、筋道を立てて論理的に考える思考法です。事実や証拠に基づいて、因果関係を明確にしながら結論を導き出します。

・既存の情報や事実に基づく
・筋道を立てて考える
・一つの正解に向かって進む
・効率性を重視する
・常識や前提を疑う
・多角的な視点から考える
・複数の可能性を探る
・創造性を重視する

両者は対立するものではなく、補完関係にある思考法です。ビジネスシーンでは、創造的なアイデアを生み出すためにラテラルシンキングを活用し、そのアイデアを実現可能なものにするためにロジカルシンキングを活用するという組み合わせが効果的です。
2-2. クリティカルシンキング(批判的思考)との違い
クリティカルシンキングは、情報や主張を客観的に分析し、その妥当性や信頼性を評価する思考法です。

・情報を客観的に分析する
・根拠の妥当性を検証する
・バイアスや誤りを見つける
・合理的な判断を下す
・新しい視点を積極的に取り入れる
・直感や偶然性を重視する
・「常識」を疑い、枠を超える
・革新的なアイデアを生み出す

クリティカルシンキングが既存の情報や主張の妥当性を検証するのに対し、ラテラルシンキングは新しい可能性や視点を探索します。両方の思考法をバランスよく活用することで、創造的かつ現実的な問題解決が可能になります。
3. ラテラルシンキングが注目される理由
近年、ビジネスの世界でラテラルシンキングが注目されている背景には、いくつかの社会的・経済的要因があります。
3-1. 既成概念が通用しなくなっている
デジタル技術の急速な発展やグローバル化の進展により、従来のビジネスモデルや常識が通用しなくなってきています。VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代と呼ばれる現代では、従来の延長線上にない発想や解決策が求められるようになりました。
例えば、スマートフォンの登場によって、カメラ、音楽プレーヤー、電話、コンピュータなどが一つの端末に統合されるという発想は、従来の常識を覆すラテラルシンキングの好例と言えます。
3-2. 新しいアイデアの創出が求められている
市場の成熟化やグローバル競争の激化により、企業は差別化のための新しいアイデアや価値を常に生み出す必要があります。イノベーションの源泉となる創造的思考の重要性が高まっているのです。
また、AI(人工知能)の発達により、単純作業や論理的な処理は機械に代替される可能性が高まっています。そのような中で、人間にしかできない創造的な思考や発想が一層重要になっているのです。
3-3. 複雑な社会課題の解決に必要
環境問題、少子高齢化、格差拡大など、現代社会が直面する課題は複雑で従来の方法では解決が難しいものが増えています。これらの課題に対処するためには、既存の枠組みを超えた新しい発想や視点が必要です。
例えば、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けて、環境保護と経済発展を両立させるような新しいビジネスモデルの創出には、ラテラルシンキングが欠かせません。
4. ラテラルシンキングの具体例と例題
ラテラルシンキングの特徴を理解するために、具体的な例題とその解き方を見ていきましょう。これらの例題は、前提を疑い、多角的に考えることの重要性を示しています。
4-1. 13個のオレンジを3人に分ける方法
問題
13個のオレンジを3人に平等に分けるにはどうすればよいでしょうか?
この問題に対する一般的な考え方は、13÷3=4余り1となり、完全に平等に分けることはできないというものです。しかし、ラテラルシンキングでは前提を疑い、別の角度から考えます。
解答例
オレンジをジュースにして3人に均等に分ける。
または、オレンジ10個を3人に3個ずつ配り、残りの3個は各人に1個ずつ皮をむいたものを渡す。
あるいは、1人目に4個、2人目に4個、3人目に4個渡し、残りの1個は3人で共有する。
この例題では、「オレンジは個数として分けなければならない」「オレンジは形を変えてはならない」といった暗黙の前提を疑うことがポイントです。状況や目的に応じて、柔軟に発想を変えることがラテラルシンキングの特徴です。
4-2. マカロニの測り方
問題
料理のレシピに「マカロニ300g」と書かれていますが、家にある計りの上限は100gです。どうやって正確に300gのマカロニを測ればよいでしょうか?
一般的な解決策としては、100gずつ3回に分けて測るという方法が考えられます。しかし、ラテラルシンキングでは別の視点からの解決策を探ります。
解答例
マカロニの入った袋全体の重さを測り、そこからマカロニ以外の重さ(袋の重さ)を引く。
または、水を入れた容器の重さを測り、そこにマカロニを入れて再度重さを測り、その差が300gになるまでマカロニを入れる。
さらに、マカロニの個数と重さの関係を計算し、個数で数える方法もある。
この問題では、「計りで直接測る」という前提を疑い、間接的な測定方法や代替手段を考えることがポイントです。限られた資源や制約の中で最適な解決策を見つけるためのラテラルシンキングの実例と言えます。
4-3. ウミガメのスープ問題
問題
ある男性がレストランでウミガメのスープを注文しました。一口飲んだ後、男性は「これは本物のウミガメのスープだ」と言い、その後自殺してしまいました。なぜでしょうか?
この問題は「ラテラル思考クイズ」として知られるもので、質問者に「はい」「いいえ」で答えられる質問をしながら謎を解いていきます。
解答例
この男性は以前、難破した船から生き残った際に、仲間と共に救命ボートに乗っていました。食料が尽きた彼らは、くじ引きで決めた一人を殺して食べることにしました。男性の妻がその犠牲者となり、男性は妻の肉を食べて生き延びました。
その後、レストランで注文したウミガメのスープの味が、かつて食べた「人肉」の味と同じだと気づき、それが実は人肉のスープであり、自分はまた人肉を食べてしまったという罪悪感から自殺したのです。
この例題では、表面的な情報だけでなく、背景にある文脈や心理的要因を探ることがポイントです。ラテラルシンキングでは、問題の本質を見極め、直感的でユニークな視点から解決策を導き出すことが求められます。
4-4. アイスクリームのカップ回収問題
問題
アイスクリーム販売会社が、使用済みのカップを回収してリサイクルしたいと考えています。しかし、顧客はカップを捨ててしまうため、回収率が低いという問題があります。どうすれば効果的に回収できるでしょうか?
この問題に対して、従来の発想では「回収ボックスを増やす」「回収キャンペーンを行う」といった解決策が考えられます。しかし、ラテラルシンキングではより革新的なアプローチを探ります。
解答例
アイスクリームのカップそのものを食べられる素材で作る。
または、カップを返却すると次回購入時に割引されるシステムを導入する。
さらに、カップの中に「当たり」のシールを貼り、回収時に景品がもらえるようにする。
この例題では、「カップを回収する」という前提自体を見直し、別の視点から問題解決を図ることがポイントです。ラテラルシンキングでは、問題の設定そのものを変えることで、革新的な解決策を見つけることができます。
5. ラテラルシンキングのメリットとデメリット
ラテラルシンキングを活用する上で、そのメリットとデメリットを理解しておくことが重要です。
5-1. ラテラルシンキングのメリット

従来の常識や固定観念にとらわれないため、革新的でユニークな発想やアイデアを生み出すことができます。競合他社との差別化や新たな市場の創出につながる可能性があります。
複雑な問題に対して、従来の分析的アプローチでは膨大な時間がかかることがあります。ラテラルシンキングでは、直感や偶然性を重視することで、短時間で効果的な解決策を見つけられることがあります。


一つの正解だけを求めるのではなく、多角的な視点から複数の可能性を探るため、様々な選択肢や代替案を生み出すことができます。状況変化に応じた柔軟な対応が可能になります。
新しい発想やアイデアを探求するプロセスは、チームの創造性を刺激し、モチベーションの向上につながります。マンネリ化した職場環境の活性化にも効果的です。

5-2. ラテラルシンキングのデメリット

自由な発想を重視するあまり、現実的でない結論や、本来の課題解決からかけ離れたアイデアが生まれてしまうことがあります。実行可能性の検証が必要です。
創造的なアイデアが必ずしも効果的な解決策につながるとは限りません。検証や評価のプロセスが不可欠です。


保守的な組織文化や階層的な意思決定構造の中では、ラテラルシンキングによる革新的なアイデアが受け入れられにくいことがあります。変化への抵抗を乗り越える工夫が必要です。
従来の方法と比べて、成果の予測や計測が難しいことがあります。リスク管理や評価基準の設定に工夫が必要です。

ラテラルシンキングは万能ではなく、ロジカルシンキングやクリティカルシンキングと組み合わせて活用することで、その効果を最大化することができます。状況や課題に応じて、適切な思考法を選択することが重要です。
6. ビジネスにおけるラテラルシンキングの活用方法
ラテラルシンキングはビジネスシーンのさまざまな場面で活用することができます。具体的な活用方法を見ていきましょう。
6-1. 他社にはない商品・サービスを生み出す
市場が成熟し、類似した商品やサービスが溢れる現代において、差別化は企業の生き残りに不可欠です。ラテラルシンキングを活用することで、競合他社とは一線を画した独自の価値提案が可能になります。
例えば、以下のような視点で新商品・サービス開発を考えることができます:
- 既存の商品・サービスの前提や常識を疑う
- 顧客の潜在的なニーズや課題を多角的に捉える
- 異なる業界や分野のアイデアを取り入れる
- 「もし〜だったら?」という仮説思考を活用する
成功事例として、カーシェアリングサービスが挙げられます。従来の「車は所有するもの」という前提を覆し、「必要な時に必要なだけ利用する」という新しい価値観を創出しました。
6-2. 新しい発想をすることで課題を成功へと導く
ビジネスの現場では、従来の方法では解決が困難な課題に直面することがあります。そのような場合、ラテラルシンキングによる発想の転換が突破口となることがあります。
例えば、以下のような視点で課題解決に取り組むことができます:
- 問題の設定自体を見直す
- 制約条件を逆に機会として捉える
- 「なぜ?」を繰り返し、根本原因を探る
- 複数の視点から解決策を模索する
例えば、ある飲食店が「客単価を上げる」という課題に直面した際、単純に価格を上げるのではなく、「お客様が喜んでお金を使いたくなる新しい体験」を提供するという視点から、料理のパフォーマンス化や食材の物語性の強化など、付加価値を高める工夫を行うといった解決策が考えられます。
6-3. 組織変革や働き方改革への応用
ラテラルシンキングは、組織の制度や仕組み、働き方の改革にも応用できます。従来の常識や前例にとらわれず、新しい組織のあり方や働き方を模索することができます。
例えば、以下のような視点で組織改革に取り組むことができます:
- 「なぜそのルールや制度があるのか」を根本から問い直す
- 異業種や異文化の組織運営方法から学ぶ
- 固定観念を取り払い、理想の状態から逆算する
- 多様な視点や価値観を積極的に取り入れる
例えば、リモートワークの導入において、単に「オフィスでの作業をリモートに置き換える」のではなく、「仕事の本質は何か」「成果をどう評価するか」といった根本的な問いから、時間や場所にとらわれない新しい働き方のモデルを構築するといった取り組みが挙げられます。
7. ラテラルシンキングの進め方
ラテラルシンキングを実践するための基本的なステップを紹介します。これらのプロセスを意識することで、より効果的に創造的な問題解決が可能になります。
7-1. 現状の不満に気づく
ラテラルシンキングの第一歩は、現状に対する「違和感」や「不満」に気づくことです。「当たり前」を疑い、「もっと良い方法があるのでは?」と問いかける姿勢が重要です。
この段階では、以下のような問いかけが有効です:
- 現状のやり方に違和感はないか
- 顧客や関係者の隠れた不満はないか
- 「当然」「常識」とされていることに無駄や非効率はないか
- 自分自身が感じている小さな引っかかりは何か
7-2. 不満が生じる原因をさぐる
気づいた不満や違和感の根本原因を探るために、「なぜ?」を繰り返し問いかけます。表面的な症状ではなく、本質的な課題を見極めることが重要です。
例えば、「会議が長引く」という不満があれば:
- なぜ会議が長引くのか? → 議論が脱線するから
- なぜ議論が脱線するのか? → 会議の目的が明確でないから
- なぜ目的が明確でないのか? → 事前の準備や共有が不足しているから
- なぜ準備が不足しているのか? → 準備の重要性が認識されていないから
- なぜ認識されていないのか? → 効率的な会議の経験がないから
このように根本原因を探ることで、より本質的な解決策を見つけやすくなります。
7-3. 解決策としての理想像を描く
根本原因が明らかになったら、「制約がなければどうなるか」「理想的な状態はどのようなものか」を自由に発想します。この段階では、現実的な制約を一旦脇に置き、大胆に理想を描くことが重要です。
以下のような問いかけが有効です:
- もし魔法が使えるとしたら、この問題をどう解決するか
- 予算や時間の制約がなければ、どのような解決策が考えられるか
- 10年後、この問題はどのように解決されているだろうか
- 全く異なる業界では、類似の問題をどのように解決しているか
7-4. 理想の実現方法を見つけ出す
描いた理想像を現実の制約の中でどう実現するかを考えます。この段階では、アイデアの実現可能性や効果を検証し、具体的な行動計画に落とし込むことが重要です。
以下のような視点が有効です:
- 理想と現実のギャップを埋めるためにできることは何か
- リソースの制約の中で、最も効果的なアプローチは何か
- 段階的に実現するための最初のステップは何か
- 誰と協力すれば実現可能性が高まるか
例えば、「ペーパーレスオフィス」という理想に対して、一気に全ての書類を電子化するのではなく、まずは会議資料から電子化を始め、徐々に範囲を広げていくといった具体的な実現方法を考えます。
ラテラルシンキングの進め方のポイント
ラテラルシンキングのプロセスでは、従来の常識や前提を疑い、多角的な視点で問題を捉えることが重要です。特に「理想像を描く」段階では、現実的な制約にとらわれず、自由な発想を心がけましょう。また、このプロセスは必ずしも直線的に進むわけではなく、各ステップを行き来しながら思考を深めていくことが大切です。
8. ラテラルシンキングを身につける方法
ラテラルシンキングは訓練によって身につけることができる思考法です。効果的なトレーニング方法を紹介します。
8-1. 複数の視点から考える
ひとつの問題や状況を、異なる立場や視点から考える習慣をつけましょう。多様な視点を持つことで、新しい気づきや発想が生まれやすくなります。
以下のような練習方法が効果的です:
- ある問題について、異なる職業や立場(顧客、競合、子供、高齢者など)の視点で考えてみる
- 「もし私が〇〇だったら、この問題をどう捉えるか」と想像する
- チームで問題解決する際に、意図的に異なる役割や視点を割り当てる
例えば、新商品開発において、「開発者」「営業担当」「顧客」「競合企業」「5年後の自社」など、様々な視点から商品の価値や課題を検討することで、より包括的な理解と創造的なアイデアが生まれます。
8-2. 思考方法を変えてみる
普段とは異なる思考プロセスや発想法を意識的に取り入れることで、思考の柔軟性が高まります。以下のような方法を試してみましょう:
- 逆転思考:問題を逆から考える(「どうすれば失敗するか」を考えることで成功要因を探る)
- 類推思考:異なる分野や対象に置き換えて考える(自然現象や生物からヒントを得るなど)
- 制約思考:あえて制約を設けて考える(「もし予算が10分の1だったら」など)
- 無作為連想法:無関係な言葉や概念を組み合わせて新しいアイデアを生む
例えば、「オフィスの生産性向上」という課題に対して、「蟻の巣の効率性からヒントを得る」「もし電気が使えなかったらどうするか」といった視点で考えることで、新たな気づきが生まれることがあります。
8-3. ラテラルシンキングを鍛えるツール
ラテラルシンキングを効果的に鍛えるためのツールやフレームワークを活用しましょう。代表的なものを紹介します。

エドワード・デ・ボノ博士が考案した思考法で、6つの異なる「帽子」(視点)を使い分けて考えるものです。
・白色の帽子:事実や情報に焦点を当てる
・赤色の帽子:感情や直感に焦点を当てる
・黒色の帽子:リスクや問題点を指摘する
・黄色の帽子:利点やメリットを考える
・緑色の帽子:新しいアイデアや可能性を探る
・青色の帽子:思考プロセス全体を管理する
アレックス・F・オズボーンが考案した創造的思考のためのチェックリストです。
・他の用途はないか
・応用できないか
・修正できないか
・拡大できないか
・縮小できないか
・代用できないか
・再配列できないか
・逆にできないか
・結合できないか

これらのツールを意識的に活用することで、思考の幅を広げ、創造的なアイデアを生み出す力を養うことができます。
8-4. 日常に取り入れるラテラルシンキング
ラテラルシンキングは、特別なワークショップやセッションだけでなく、日常の思考や行動の中に取り入れることで徐々に身についていきます。以下のような習慣を心がけましょう:
- 日常の「当たり前」に疑問を投げかける習慣をつける
- 「なぜ?」を5回繰り返して根本原因を探る
- 新しい経験や異なる分野の知識に触れる機会を増やす
- 失敗や間違いを学びの機会として捉える
- 定期的に「もし〜だったら?」という仮定の質問を自分に投げかける
例えば、通勤経路を意図的に変えてみる、普段読まない分野の本を読む、異業種の人との対話の機会を増やすなど、小さな変化を日常に取り入れることで、思考の柔軟性を高めることができます。
9. ラテラルシンキング獲得のための練習問題
ラテラルシンキングの能力を高めるための練習問題を紹介します。これらを定期的に解くことで、思考の柔軟性が徐々に身についていきます。
9-1. 日常生活での練習問題
日常のシーンを題材にした練習問題を通じて、固定観念を外す訓練をしましょう。
問題1:輪ゴムの使い方
輪ゴムの使い方をできるだけ多く考えてください。通常の使い方以外のユニークな用途を考えることが目的です。
問題2:靴下の片方がなくなった時
お気に入りの靴下の片方がなくなってしまいました。残った一方をどのように活用できるでしょうか?できるだけ多くのアイデアを考えてください。
問題3:時間を節約する方法
朝の準備時間を短縮するための創造的なアイデアをできるだけ多く考えてください。従来の「早起きする」「前日に準備する」以外の発想を重視します。
これらの問題に対して、まずは思いつくままにアイデアを出し、その後、「オズボーンのチェックリスト」などのツールを使って、さらにアイデアを広げてみましょう。質よりも量を重視し、奇抜なアイデアほど歓迎する姿勢が大切です。
9-2. ビジネスシーンでの練習問題
ビジネスの文脈に沿った練習問題も効果的です。実際の業務課題に近い設定で考えることで、実践的なスキルが身につきます。
問題1:会議の効率化
長時間の会議が多く、生産性が低下しています。会議を効率化するための革新的なアイデアを考えてください。従来の「アジェンダを設定する」「タイムキーパーを置く」以外の発想で考えましょう。
問題2:新しい顧客獲得
予算を使わずに新規顧客を獲得する方法を考えてください。従来の営業活動やマーケティング手法とは異なる、創造的なアプローチを模索しましょう。
問題3:オフィススペースの活用
コロナ禍以降、出社率が下がり、オフィススペースに余裕ができました。この余ったスペースを創造的に活用するアイデアを考えてください。単なる「サブリース」以外の発想で考えましょう。
これらの問題に対して、6色シンキングハットなどのツールを活用しながら、多角的な視点からアイデアを出してみましょう。また、チームで取り組むことで、さらに多様な発想が生まれる効果も期待できます。
9-3. 脳トレパズルとしてのラテラルシンキング
ラテラルシンキングは脳トレパズルとしても人気があります。以下のような問題を定期的に解くことで、思考の柔軟性を鍛えることができます。
問題1:両方とも正しい
「私は嘘をついています」という文は真実でしょうか、それとも嘘でしょうか?
問題2:穴をより大きく
紙に開けた穴を、紙を切ることなくより大きくするにはどうすればよいでしょうか?
問題3:停電時の高層ビル
停電が発生し、高層ビルのエレベーターが止まってしまいました。あなたは最上階の50階にいて、重要な会議資料を1階のオフィスに届ける必要があります。どうすれば最も効率的に届けられるでしょうか?
これらのパズルは一見単純ですが、従来の思考法では解決が難しいものです。発想を転換し、前提を疑うことで新たな解決策が見えてきます。
10. まとめ:ラテラルシンキングを活かした創造的問題解決
ラテラルシンキング(水平思考)は、従来の常識や固定観念にとらわれず、多角的な視点から創造的なアイデアや解決策を生み出す思考法です。変化が激しく予測困難な現代社会において、この思考法の重要性はますます高まっています。
ラテラルシンキングの特徴は以下のとおりです:
- 前提や常識を疑う
- 多角的な視点から考える
- 創造的で革新的なアイデアを生み出す
- 直感や偶然性を重視する
ビジネスシーンでは、新商品・サービスの開発、課題解決、組織変革など、様々な場面でラテラルシンキングを活用することができます。特に、従来の方法では解決が難しい複雑な問題に直面した際に、その真価を発揮します。
ラテラルシンキングを身につけるためには、以下のような取り組みが効果的です:
- 複数の視点から考える習慣をつける
- 思考方法を意識的に変えてみる
- 6色シンキングハットやオズボーンのチェックリストなどのツールを活用する
- 日常生活の中で「当たり前」を疑う習慣をつける
- 定期的に練習問題に取り組む
ラテラルシンキングは、ロジカルシンキングやクリティカルシンキングと対立するものではなく、相補的な関係にあります。創造的なアイデアを生み出すためにラテラルシンキングを活用し、そのアイデアの実現可能性や効果を検証するためにロジカルシンキングを活用するという組み合わせが効果的です。
最後に、ラテラルシンキングは一朝一夕で身につくものではありません。継続的な実践と意識的な取り組みによって、徐々に思考の柔軟性が高まっていきます。日常の小さな場面から意識して取り入れることで、創造的な問題解決能力を養い、ビジネスや人生における様々な課題に対処していきましょう。
ラテラルシンキングとロジカルシンキングはどちらが優れているのですか?
どちらが優れているというものではなく、状況や目的に応じて使い分けることが重要です。新しいアイデアや発想が必要な場面ではラテラルシンキングが、論理的な検証や実行計画が必要な場面ではロジカルシンキングが適しています。両方の思考法をバランスよく活用することで、創造的かつ現実的な問題解決が可能になります。
ラテラルシンキングは生まれつきの才能ではないのですか?
創造性に個人差はありますが、ラテラルシンキングは基本的に訓練によって習得・向上させることができる思考法です。エドワード・デ・ボノ博士は「創造性は技術であり、訓練によって習得できる」と主張しています。継続的な実践と意識的な取り組みによって、誰でも思考の柔軟性を高めることが可能です。
ラテラルシンキングはチームでも活用できますか?
はい、ラテラルシンキングはチームでの活用も非常に効果的です。多様なバックグラウンドや専門性を持つメンバーが集まることで、より多角的な視点やアイデアが生まれやすくなります。ブレインストーミングセッションや6色シンキングハットなどのワークショップを通じて、チーム全体の創造性を高めることができます。ただし、メンバー全員が批判を控え、自由な発想を尊重する姿勢が重要です。
ラテラルシンキングを日常的に鍛えるコツはありますか?
日常的にラテラルシンキングを鍛えるコツとしては、以下のような方法があります:
- 日常の「当たり前」に疑問を投げかける習慣をつける
- 意図的に異なるルートや方法を試してみる
- 様々なジャンルの本や記事を読む
- 異業種や異文化の人との交流を増やす
- 趣味や活動の幅を広げる
- 「なぜ?」「もし〜だったら?」という質問を自分に投げかける
これらの小さな習慣が、徐々に思考の柔軟性を高めていきます。