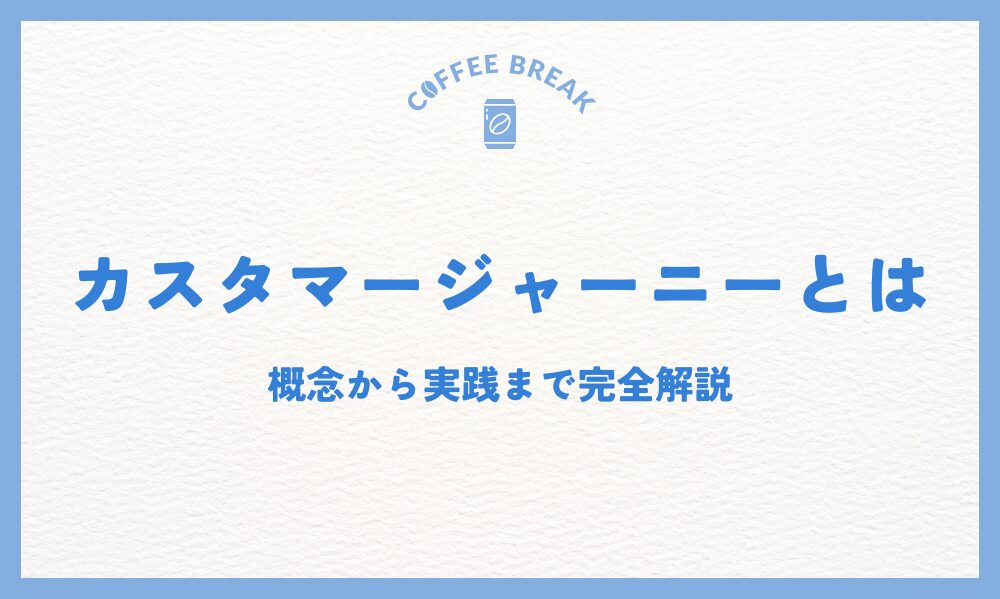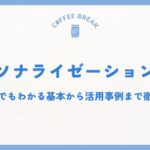カスタマージャーニーは現代マーケティングにおいて重要な概念です。顧客が商品やサービスを認知し、購入・利用に至るまでの「旅路」を可視化することで、効果的なマーケティング戦略を立てることができます。本記事では、カスタマージャーニーの基本概念から作成方法、実践的な活用方法まで詳しく解説します。古いと言われる理由や最新の考え方も踏まえ、ビジネスに実際に役立つ形でお伝えします。
目次
カスタマージャーニーとは
カスタマージャーニーとは、直訳すると「顧客の旅」という意味です。顧客が自社の商品やサービスを知り、興味を持ち、比較検討し、購入、そして利用するまでの一連のプロセスを「旅」に例えた考え方です。
マーケティングにおいては、顧客視点でこの「旅」を理解することが重要です。顧客がどのような経路をたどって購買に至るのか、各ステップでどのような感情や思考を持っているのかを把握することで、効果的なマーケティング施策を展開できます。
カスタマージャーニーの基本的な構成要素
カスタマージャーニーは主に以下の要素で構成されています:
- フェーズ(段階):認知、興味、比較検討、購入、利用、再購入などの段階
- 行動:各フェーズでの具体的な顧客行動
- タッチポイント:顧客と企業が接点を持つ場面や媒体
- 思考・感情:各段階での顧客の心理状態
- 課題・ペインポイント:顧客が直面する問題や障壁
- 施策:各段階で企業が提供する価値や取るべきアクション
これらの要素を体系的に整理することで、顧客体験を包括的に理解し、各段階に応じた適切な施策を打つことができます。
カスタマージャーニーが古いと言われる理由
近年、「カスタマージャーニーは古い」という声も聞かれるようになりました。これには主に以下の理由があります。
現代の消費者行動は従来の直線的なプロセスとは異なり、より複雑で予測困難なパターンを示すようになっています。スマートフォンの普及やSNSの発達により、情報収集や比較検討のプロセスが大きく変化しました。

特に注目すべきは「パルス型消費」と呼ばれる新しい消費行動パターンです。これは、特定のきっかけによって衝動的に購買が発生し、従来のような段階的なプロセスを経ないケースが増えていることを指します。
パルス型消費:SNSでの口コミやインフルエンサーの投稿など、突発的なきっかけで購買が発生する消費行動。従来の段階的なプロセスを経ないことが特徴です。
しかし、このような変化があっても、カスタマージャーニーの考え方自体が無効になったわけではありません。むしろ、複雑化した顧客行動を理解するためのフレームワークとして、より進化した形で活用されるべきと言えます。
顧客の心理プロセスについては「AIDMA(アイドマ)の法則は古い?今こそ使える理由と最新モデルとの違いを徹底比較」も参考になります。
カスタマージャーニーの設計により得られる効果
カスタマージャーニーを適切に設計・活用することで、ビジネスには様々なメリットがもたらされます。ここでは主要な効果について解説します。
顧客視点で購買プロセスを認識できる
カスタマージャーニーの最大の価値は、企業視点ではなく顧客視点でビジネスを捉え直せることです。製品やサービスの機能や特徴ではなく、顧客が実際に何を考え、どう行動し、どのような体験をしているかに焦点を当てることができます。
この視点の転換により、見落としていた顧客のニーズや課題が明らかになり、新たな改善点や機会を発見することが可能です。また、顧客の感情や思考を理解することで、より共感的なコミュニケーションが実現します。
各プロセスのKPIと具体的な施策が明確になる
カスタマージャーニーを可視化することで、購買プロセスの各段階における重要指標(KPI)と最適な施策が明確になります。例えば:
| フェーズ | KPI例 | 施策例 |
|---|---|---|
| 認知 | リーチ数、認知度 | 広告、SEO対策、PR |
| 興味 | サイト訪問数、滞在時間 | コンテンツマーケティング |
| 検討 | 資料請求数、問い合わせ数 | 比較表、事例紹介、FAQの充実 |
| 購入 | コンバージョン率、購入数 | 限定オファー、購入フロー改善 |
| 利用 | 継続率、利用頻度 | サポート強化、使い方ガイド |
| 推奨 | 再購入率、紹介数 | ロイヤルティプログラム、レビュー促進 |
各フェーズに適したKPIを設定し、それを改善するための具体的な施策を実施することで、効率的なマーケティング活動が可能になります。
社内での認識を共通化できる
カスタマージャーニーマップという形で可視化することで、部門を超えた共通認識が生まれます。マーケティング部門だけでなく、営業、製品開発、カスタマーサポートなど、顧客との接点を持つすべての部門が同じ顧客像と購買プロセスを理解することで、一貫性のある顧客体験を提供できます。
顧客ロイヤルティの向上につながる
カスタマージャーニー全体を通して一貫した質の高い体験を提供することで、顧客満足度とロイヤルティが向上します。特に、従来見落とされがちだった購入後のフェーズ(利用、サポート、再購入など)に注目することで、長期的な顧客関係の構築が可能になります。
顧客生涯価値(LTV)を高めるためには、初回購入だけでなく、継続的な関係構築が重要であり、カスタマージャーニーの考え方はこの点で非常に有効です。
カスタマージャーニーマップのテンプレート
カスタマージャーニーを可視化する手法として「カスタマージャーニーマップ」があります。ここでは、基本的なテンプレートの構成要素と、各購買プロセスについて解説します。
購買プロセスの解説
カスタマージャーニーマップの横軸には、一般的に以下のような購買プロセスのフェーズが設定されます。
1|ニーズの認識
顧客が自分のニーズや問題点を認識する段階です。この時点では、顧客は具体的な解決策やブランドを認識していないことが多く、漠然とした課題意識を持っています。

この段階での重要なポイントは、顧客の潜在ニーズを喚起するコンテンツや情報を提供することです。問題提起型の記事やソーシャルメディアでの情報発信が効果的です。
2|商品の認知
顧客が自分のニーズを満たす可能性のある商品やサービスを認知する段階です。このフェーズでは、顧客は様々な情報源から解決策に関する情報を集め始めます。

この段階では、自社の商品やサービスが問題解決に役立つことを認知してもらうことが重要です。SEO対策、コンテンツマーケティング、SNS広告などが有効な施策となります。
3|比較検討
顧客が複数の選択肢を比較し、最適な解決策を検討する段階です。この段階では、顧客は様々な製品やサービスの機能、価格、使い勝手などを詳しく調査します。

この段階では、競合との差別化ポイントを明確に伝えることが重要です。比較表、事例紹介、詳細な製品情報、レビューなどが有効なコンテンツとなります。
4|購入・導入
顧客が最終的な意思決定を行い、実際に購入や契約をする段階です。この段階では、購入プロセスの簡便さや安心感が重要な要素となります。

この段階では、購入障壁を取り除き、スムーズな購入体験を提供することが重要です。簡単な購入手続き、明確な価格表示、安全な決済システムなどが効果的です。
5|利用
顧客が実際に商品やサービスを使用する段階です。この段階の顧客体験は、満足度やロイヤルティ形成に大きな影響を与えます。

この段階では、充実したサポートとわかりやすい使用ガイドを提供することが重要です。オンボーディング、チュートリアル、FAQなどが効果的な施策となります。
6|継続・リピート購入
顧客が継続的に製品やサービスを利用し、場合によっては追加購入や他者への推奨を行う段階です。この段階は顧客生涯価値を最大化するために非常に重要です。

この段階では、顧客ロイヤルティを高め、長期的な関係を構築することが重要です。アップセル・クロスセル、ロイヤルティプログラム、定期的な価値提供などが効果的な施策となります。
各プロセスに設定する4項目
カスタマージャーニーマップの縦軸には、一般的に以下のような要素が設定されます。
1|行動
各フェーズで顧客が取る具体的な行動を記述します。例えば「Google検索する」「公式サイトを訪問する」「SNSで口コミを確認する」など、できるだけ具体的に記載します。
行動を詳細に把握することで、顧客のプロセスをより正確に理解し、各行動に対応した最適な施策を考えることができます。
2|タッチポイント
顧客と企業が接点を持つ場面や媒体を記述します。例えば「検索エンジン」「自社Webサイト」「SNS」「メールマガジン」「カスタマーサポート」などが含まれます。
タッチポイントを明確にすることで、顧客接点の最適化や不足している接点の補強が可能になります。オムニチャネルでの一貫した体験を提供するためにも重要です。
3|思考・感情
各フェーズでの顧客の心理状態、不安、期待、疑問などを記述します。これは共感マップのように顧客の内面を理解するための重要な要素です。
例えば「価格が適正か不安」「導入後のサポートは充実しているか」「使いこなせるだろうか」といった心理状態を把握することで、それらの不安や疑問に対応したコミュニケーションが可能になります。
4|提供できる価値
各フェーズで企業が提供できる価値やサポートを記述します。顧客の行動や感情に対応し、最適なタイミングで適切な価値を提供することが重要です。
例えば「詳細な比較情報の提供」「簡単な申込みプロセス」「充実したチュートリアル」「定期的な活用事例の共有」などが含まれます。
カスタマージャーニーマップとペルソナの違いは何ですか?
ペルソナは「誰が」に焦点を当てた架空の顧客像であるのに対し、カスタマージャーニーマップは「どのように」に焦点を当てた顧客行動の流れです。ペルソナを先に設定し、そのペルソナに基づいてカスタマージャーニーマップを作成するのが一般的です。両者を組み合わせることで、より深い顧客理解が可能になります。
カスタマージャーニーマップの作り方の手順
カスタマージャーニーマップを効果的に作成するための具体的な手順を解説します。
STEP1:目的とスコープの設定
まず、カスタマージャーニーマップを作成する目的を明確にします。例えば「Webサイトのコンバージョン率向上」「新規顧客獲得プロセスの改善」「既存顧客のロイヤルティ向上」など、具体的な目的を定めます。
また、対象とする範囲(スコープ)も決定します。特定の商品やサービスに絞るのか、特定の顧客セグメントに絞るのか、購買前後どこまでのプロセスを含めるのかなどを明確にしておきます。
STEP2:ペルソナの設定
カスタマージャーニーマップは、特定のペルソナ(顧客像)に基づいて作成します。ペルソナには以下のような要素を含めます:
- 基本属性(年齢、性別、職業、家族構成など)
- 行動特性(情報収集方法、購買習慣など)
- 価値観・関心事(重視するポイント、ライフスタイルなど)
- 課題・ニーズ(直面している問題、達成したい目標など)
複数のペルソナが存在する場合は、最も重要なペルソナや代表的なペルソナを選んでマップを作成します。必要に応じて複数のマップを作成することも可能です。
STEP3:顧客データの収集・分析
仮説ではなく実際のデータに基づいたカスタマージャーニーマップを作成するために、様々な顧客データを収集・分析します。データソースには以下のようなものがあります:
- 顧客インタビューや調査結果
- Webサイトのアクセス解析データ
- CRMデータ(顧客の購買履歴など)
- カスタマーサポートへの問い合わせ内容
- SNSでの顧客の声や評価
これらのデータを分析し、顧客の行動パターン、タッチポイント、ペインポイントなどを洗い出します。
STEP4:フェーズの設定
顧客の購買プロセスを適切なフェーズに分割します。一般的なフェーズとしては前述の6段階(ニーズ認識、認知、検討、購入、利用、継続)が使われますが、業種や商材によって最適なフェーズ分けは異なります。
BtoBビジネスの場合は、情報収集、ロングリスト作成、ショートリスト作成、評価、交渉、契約といったフェーズ分けが適している場合もあります。
STEP5:各要素の洗い出し
各フェーズにおける顧客の行動、タッチポイント、思考・感情、ペインポイントなどを詳細に洗い出します。この際、収集したデータや顧客インタビューの結果を参照し、できるだけ現実に即した内容にすることが重要です。
各要素は箇条書きでもよいですが、できるだけ具体的に記述することで、より実用的なマップになります。
STEP6:施策の検討
各フェーズ、特に課題やペインポイントが見つかった箇所に対して、具体的な解決策や改善施策を検討します。施策を検討する際のポイントは以下の通りです:
- 顧客の問題やニーズに対応しているか
- 適切なタイミングとタッチポイントで提供できるか
- 実現可能性と期待される効果のバランスは取れているか
- 優先順位付けは適切か
施策が決まったら、それを実行するための具体的なアクションプランとスケジュールも作成します。
STEP7:マップの完成と共有
上記のステップで集めた情報を整理し、カスタマージャーニーマップとして視覚化します。マップの形式は様々ですが、横軸にフェーズ、縦軸に各要素(行動、タッチポイント、感情など)を配置する表形式が一般的です。
完成したマップは関係者全員に共有し、チーム内での共通理解を促進します。可能であれば、マップを印刷して会議室に掲示するなど、常に参照できる環境を整えると効果的です。
STEP8:PDCAサイクルの実施
カスタマージャーニーマップは一度作成して終わりではなく、継続的に更新・改善していくものです。施策の実施結果や新たな顧客データを基に、定期的にマップを見直し、必要に応じて修正します。
PDCAサイクルの例
- Plan(計画):カスタマージャーニーマップに基づいた施策計画
- Do(実行):施策の実施
- Check(評価):KPIの測定、顧客フィードバックの収集
- Act(改善):評価結果に基づくマップと施策の修正
ユーザー体験を高めるパーソナライゼーションについては「パーソナライゼーションとは?初心者でもわかる基本から活用事例まで徹底解説」もご覧ください。
カスタマージャーニーマップを作る際の注意点
カスタマージャーニーマップを作成する際には、以下の点に注意すると、より有効なマップが作成できます。
企業視点で考えない
カスタマージャーニーマップの最も重要なポイントは、顧客視点に立つことです。自社の製品やサービスの優れた点をアピールするための道具ではなく、顧客が実際にどのような体験をしているかを理解するためのツールであることを忘れないようにしましょう。
そのためには、主観的な憶測や希望的観測を排除し、実際の顧客データや声に基づいてマップを作成することが重要です。可能であれば、実際の顧客にマップの内容を確認してもらうとより正確になります。
プロセスごとにデータの収集・分析を行う
カスタマージャーニーの各フェーズにおいて、適切なデータを収集・分析することが重要です。定性データ(顧客インタビュー、アンケート結果など)と定量データ(Webアクセス解析、コンバージョン率など)の両方を活用し、バランスの取れた分析を行いましょう。
特に重要なのは、各フェーズの移行率や離脱率、タッチポイントごとの効果測定です。これらのデータを基に、改善すべきポイントを特定できます。
定期的に見直しを行う
カスタマージャーニーは静的なものではなく、市場環境や顧客行動の変化に応じて常に変化します。そのため、定期的にマップを見直し、最新の状況を反映させることが重要です。
特に、新しい競合の参入、テクノロジーの進化、社会的トレンドの変化などがあった場合は、それらがカスタマージャーニーにどのような影響を与えるかを検討し、必要に応じてマップを更新しましょう。

カスタマージャーニーの実践的な活用事例
カスタマージャーニーの考え方を実際のビジネスでどのように活用できるか、具体的な事例を紹介します。
Webサイト改善への活用
カスタマージャーニーマップは、Webサイトの構造やコンテンツ設計の改善に非常に有効です。各購買段階で顧客が必要とする情報を理解し、それに合わせたコンテンツを適切な場所に配置することで、コンバージョン率の向上が期待できます。
例えば、比較検討段階の顧客には詳細な製品比較表や事例集を、購入段階の顧客には簡単な申込みフォームや安心保証に関する情報を提供するといった具合です。
コンテンツマーケティングへの活用
カスタマージャーニーの各段階に合わせたコンテンツ戦略を立てることで、より効果的なコンテンツマーケティングが可能になります。各段階で顧客が抱える疑問や課題に対応したコンテンツを作成し、適切なタイミングで提供します。
| ジャーニー段階 | コンテンツ例 |
|---|---|
| ニーズ認識 | 問題提起型ブログ記事、インフォグラフィック |
| 認知 | 基礎知識解説、ガイド記事 |
| 検討 | 比較記事、事例紹介、専門的解説 |
| 購入 | FAQ、購入ガイド、レビュー |
| 利用 | 使い方ガイド、チュートリアル動画 |
| 継続 | 活用事例、アップデート情報、専門的コンテンツ |
メール配信・MAツールでの活用
カスタマージャーニーマップは、メールマーケティングやマーケティングオートメーション(MA)との相性が非常に良いです。顧客の購買段階や行動に応じて、適切なタイミングで最適なメッセージを送ることができます。
例えば、資料ダウンロード後の見込み客には製品の詳細情報を、デモ申込み後には導入事例や特別オファーを送るといった具合に、ジャーニーに沿ったコミュニケーションを設計できます。
顧客サポート改善への活用
カスタマージャーニーの購入後のフェーズ(利用・継続)に焦点を当てることで、顧客サポートの質を向上させることができます。顧客がどのようなタイミングでどのような問題に直面するかを理解し、先回りしてサポート体制を整えることが可能です。
FAQ拡充、チュートリアル動画作成、ヘルプセンターの改善など、顧客が自己解決できる環境を整えることで、顧客満足度向上とサポートコスト削減の両立が可能になります。
組織横断的なCX向上への活用
カスタマージャーニーマップは、マーケティング部門だけでなく、営業、製品開発、カスタマーサポートなど複数部門で共有することで、組織全体での顧客体験(CX)向上に役立ちます。
各部門が自分たちの責任範囲だけでなく、顧客ジャーニー全体を理解することで、部門間の連携が強化され、一貫性のある顧客体験を提供できるようになります。
BtoBとBtoCでカスタマージャーニーに違いはありますか?
はい、大きな違いがあります。BtoBの場合は購買決定に関わる人が複数いることが多く、意思決定プロセスが複雑です。また検討期間が長く、専門的な情報が重視される傾向があります。一方、BtoCは個人の意思決定が中心で、感情的要素が強く、比較的短期間で決定されることが多いです。それぞれの特性に合わせたジャーニーマップ設計が必要です。
顧客ロイヤルティを高める方法については「ブランドロイヤルティとは?メリットと向上させる方法、成功事例まで徹底解説」も参考になります。
カスタマージャーニーは顧客体験の最適化に寄与する
本記事では、カスタマージャーニーの基本概念から作成方法、活用事例まで詳しく解説しました。カスタマージャーニーの考え方は、「古い」と言われることもありますが、むしろ複雑化した現代の消費者行動を理解するためのフレームワークとして進化しています。
重要なのは、固定的なモデルとしてではなく、顧客理解を深めるための柔軟なツールとして活用することです。定期的な見直しと更新、実際のデータに基づいた分析、そして顧客視点を常に意識することで、真に価値のあるカスタマージャーニーマップを作成できます。
顧客体験の質が競争優位性の源泉となる現代のビジネス環境において、カスタマージャーニーの考え方を取り入れることは、顧客中心の組織文化を醸成し、持続的な成長を実現するための重要なステップと言えるでしょう。