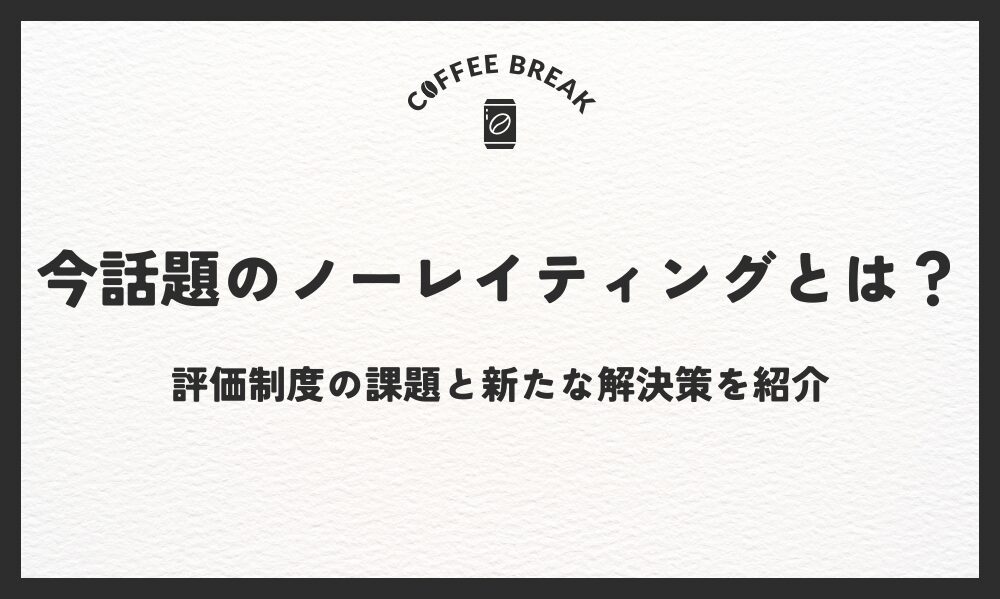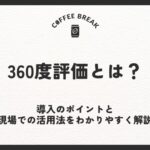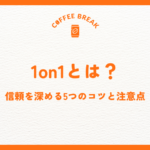働き方の多様化や人材マネジメントの変革が進む中で、近年注目されているのが「ノーレイティング」という新しい人事評価制度です。これは従来のように点数やランクで人材を評価するのではなく、上司と部下の対話を重視し、継続的なフィードバックを通じて成長を促す考え方です。
ノーレイティングを導入する企業は年々増えており、アクセンチュアやカルビーといった大手企業の取り組みが話題になっています。一方で、評価基準の不明確さや報酬制度との整合性といった課題も指摘されています。
本記事では、「ノーレイティングとは何か?」という基本から、導入企業の事例、制度のメリット・デメリット、さらに実際の導入ステップに至るまでを網羅的に解説します。これから制度の見直しを検討している人事担当者や経営者の方々にとって、実践的なヒントとなる内容をお届けします。
目次
ノーレイティングとは?基本をおさえる
ノーレイティングの定義と目的
ノーレイティングとは、「評価の格付けを行わない人事制度」を指します。従来の人事評価では、社員をA〜Dといったランクで分類したり、点数で数値化したりするケースが一般的でした。一方、ノーレイティングは「定期的な数値評価」を廃止し、対話とフィードバックによって社員の成長と成果を支援する仕組みです。
目的は、形式的な評価にとらわれず、個々の強みや成長に焦点を当てること。これにより、社員のモチベーションを高め、エンゲージメントを向上させる狙いがあります。特に、変化の激しいビジネス環境では、柔軟性のあるこの制度が注目されています。
評価の格付けをする360度評価については「360度評価とは?導入のポイントと現場での活用法をわかりやすく解説」が参考になります。
ノーレイティングとノンレーティングの違い
似た言葉として「ノンレーティング(Non-Rating)」もありますが、実は微妙な違いがあります。ノンレーティングは評価そのものを行わない方針を指し、評価制度の完全撤廃に近い意味合いです。一方、ノーレイティングは評価は行うが、スコアやランクを付けないという点で、対話やプロセスに重点を置いています。
つまり、ノーレイティングは「評価しない」のではなく、「数値で縛らない評価」と言えるでしょう。
絶対評価との違いとは?
ノーレイティングとよく混同されやすい評価手法の一つに「絶対評価」があります。どちらも他者との相対比較を前提としないという点では共通していますが、評価の目的や運用方法に明確な違いがあります。
絶対評価とは、あらかじめ定められた基準や目標に対して、社員がどの程度達成できたかを個別に評価する手法です。たとえば、「売上目標1000万円に対して90%達成」といった具合に、達成度に応じて評価が決まります。この評価手法は、成果主義を軸に置いた制度として広く採用されています。
一方、ノーレイティングはこうした「評価基準への到達度」よりも、「成長プロセス」や「本人の気づき」「対話による納得」を重視するアプローチです。評価そのものを数値化しないため、絶対評価のように基準と実績を比較するのではなく、対話やフィードバックの中で「何を学び、どう変化したか」を評価軸とするのが特徴です。
また、絶対評価は期末に一度の評価が一般的であるのに対し、ノーレイティングでは日常的な1on1やフィードバックを通じて“継続的な評価”が行われます。この運用面の違いも、制度設計の大きなポイントとなります。
つまり、絶対評価は「目標の達成度」を評価する制度であり、ノーレイティングは「人の成長と信頼関係」を軸に据えた制度と言えるでしょう。
なぜ今、ノーレイティングなのか?
評価制度への不満と働き方の変化
現代の働き方では、柔軟性や自律性が重視されるようになりました。こうした流れの中で、従来の評価制度に対する不満も高まっています。特に年功序列や定期的な査定に依存する制度は、「成果が正当に評価されない」「納得感がない」といった声につながっていました。
また、リモートワークの普及やプロジェクト単位での働き方の増加により、評価基準が曖昧になりがちです。その結果、年に一度の評価だけでは、日々の貢献を適切に把握しにくくなってきているのです。
フィードバック重視と対話文化の広がり
近年は、「上司から部下への一方通行の評価」から「双方向の対話による育成」へとシフトが進んでいます。これは、「1on1ミーティング」や「リアルタイムフィードバック」などの文化が定着してきたこととも関係しています。
ノーレイティングは、こうしたトレンドと非常に相性が良い制度です。定期的な対話を通じて、個々の課題や成果をその場で把握・対応することで、形式にとらわれず、柔軟で実践的な評価が可能となります。
従来型制度とのギャップ
従来の評価制度では、「評価のための評価」が行われることがしばしばありました。ランクをつけることが目的化し、フィードバックは後回しにされがちです。こうした制度では、部下の納得感や成長支援が置き去りになりやすく、モチベーション低下にもつながります。
ノーレイティングのメリットと可能性
対話による納得性の向上
ノーレイティングの大きなメリットのひとつが、上司と部下の「対話を重視する」点です。数値やランクでは表せないような日々の努力や改善プロセスについて、定期的に話し合うことで、被評価者にとっての納得感が高まります。
また、対話の中で得た情報は上司にとっても貴重です。業務の進捗だけでなく、部下の考えや困りごと、キャリア志向を把握できるため、より適切な指導やサポートが可能になります。結果的に、上司・部下双方の信頼関係が強化され、組織全体のエンゲージメント向上にもつながります。
評価の主観性を減らす仕組み
従来の評価制度では、評価者の主観やバイアスが入りやすいという課題がありました。ノーレイティングでは、そのリスクを軽減するために、「継続的なフィードバック」や「360度評価」など、複数の視点から社員の行動や成果を見直す仕組みが導入されることが多くなっています。
これにより、1人の上司による一括評価ではなく、チームや関係者との相互理解に基づいた評価が可能となり、評価の透明性と公平性が高まります。
人材育成との親和性
ノーレイティングは単なる評価制度ではなく、「育成ツール」としての側面も持ち合わせています。対話を通じて課題を明確にし、それに対する具体的な改善策を共有することは、部下の成長スピードを加速させます。
ノーレイティングの課題と失敗の傾向
評価者によるバラつきと属人化のリスク
ノーレイティングは評価ランクがない分、評価者の判断や観察眼がより重要になります。その結果、評価基準が不明確だったり、評価のバラつきが発生しやすくなるという課題があります。ある上司は部下の成長を重視し、別の上司は成果のみを重視する、といったケースでは、社員間での不公平感が生じる恐れがあります。
また、評価が属人化することで、「誰に評価されるか」が評価結果に大きく影響してしまう事態にもつながります。このようなリスクを回避するためには、評価者に対するトレーニングや評価プロセスのガイドライン整備が不可欠です。
報酬や昇給との連動が難しい理由
多くの企業では、評価結果をもとに報酬や昇給を決定しています。しかし、ノーレイティングでは評価の“数字”が存在しないため、報酬とどのように連動させるかが大きな課題になります。
たとえば、成果に基づいてインセンティブを支給したい場合でも、評価指標が曖昧だと「なぜこの人は昇給したのか」が周囲に伝わらず、不満や疑念が生まれやすくなります。そのため、成果・貢献・成長の各要素をどのように可視化し、報酬に反映させるかの仕組みづくりが重要になります。
従来制度との比較と周辺施策
MBO・OKRとの違い
ノーレイティングとよく比較されるのが「MBO(目標による管理)」や「OKR(目標と成果指標)」です。MBOは社員ごとに個別の目標を設定し、その達成度に応じて評価を行う制度で、目標設定と成果の関係が明確である点が特徴です。一方、OKRはより挑戦的かつ定性的な目標を設定し、組織全体の方向性と個人の活動を連携させることを重視します。
ノーレイティングはこれらと比較して、「達成度」ではなく「成長過程」や「対話の質」に焦点を当てる点が異なります。数字の達成ではなく、行動の背景や学びのプロセスに価値を見出すため、評価の視座がより内面的・長期的です。
ノーレイティングと給与の関係
評価制度と給与制度の連動は、多くの企業で切っても切れない関係です。ノーレイティングでは評価のスコアがないため、給与決定の基準が曖昧になりがちです。そのため、報酬設計においては、以下のような工夫が必要です。
- グレード制度の活用:職務内容に基づいた役割等級を明確化し、貢献度を見える化
- バリュー評価の導入:成果だけでなく、行動特性やチーム貢献も評価に加味
- ボーナスの変動化:定量的目標に対しては別途インセンティブ制度を設定
1on1・フィードバック文化との関連性
ノーレイティングを成功させる上で欠かせないのが、「1on1ミーティング」や「フィードバック文化」の浸透です。これは単なる評価制度の話ではなく、組織のコミュニケーションのあり方を根本から変える取り組みでもあります。
従来の人事評価は、年に1〜2回の評価面談を通じて、上司が部下のパフォーマンスを点数化し、給与や昇進に反映するという一方向的な流れが主流でした。しかし、ノーレイティングではその評価の軸を「対話」に移します。日常的な1on1を通じて部下の仕事や思考、感情に耳を傾け、都度フィードバックを返すことが基本になります。
このとき重要なのは、フィードバックが「評価の材料」ではなく、「育成の手段」であることです。定期的な1on1においては、成果だけでなく過程や努力、課題への姿勢などが対話の中心となり、社員の内発的動機づけを促進します。
また、上司自身のマネジメント能力やコーチングスキルも問われるため、企業として継続的な育成プログラムやトレーニングが求められます。単なる制度導入ではなく、「対話を重ねる文化」を育てることが、ノーレイティングの根幹と言えるのです。
結果として、1on1とフィードバック文化が組織全体に根付けば、評価に対する不満は減り、社員の自律性・成長意欲が高まります。ノーレイティングは、まさにこの「文化と仕組みの融合」を実現する制度設計です。
1on1ミーティングについては「1on1とは?信頼を深める5つのコツと注意点」も参考になります。
ノーレイティング導入のポイント
導入ステップ:準備→試行→定着
ノーレイティングの導入は、一度にすべてを切り替えるのではなく、段階的に進めるのが成功のカギです。一般的には以下の3ステップで進めることが推奨されています。
- 準備フェーズ
現行制度の課題分析
評価者・被評価者双方の意識調査
対話スキル向上のためのトレーニング - 試行フェーズ
一部部署やチームでのパイロット導入
1on1やフィードバック運用のテスト
トラブルや運用上の課題の洗い出し - 定着フェーズ
全社的な導入と評価制度の刷新
制度設計の見直しと改善ループの構築
継続的な教育と制度の可視化
このように、制度だけでなく“人”のマインドセットやスキルアップも並行して行うことが重要です。
人事制度全体との整合性
ノーレイティングは単独では機能しにくく、人事制度全体との整合性が不可欠です。特に、等級制度・昇格基準・報酬制度などとの連携をしっかり取ることで、制度としての一貫性と信頼性を保つことができます。
また、目標管理(MBOやOKR)との関係も明確にしておくことで、目標と評価のズレを最小限に抑えることができます。全体を通じて「何を評価するのか」「なぜ評価するのか」という共通認識の醸成が制度の成功を左右します。
評価と報酬の連携方法
報酬との連動に関しては、ノーレイティングの特性を踏まえた設計が求められます。評価が数値化されない分、報酬決定には以下のような仕組みが活用されることが増えています。
- バリュー行動評価:企業の価値観に即した行動を評価指標として活用
- 360度評価の結果反映:複数の視点でのフィードバックを評価の一部に活用
- パフォーマンスレビューと連動:プロジェクトベースでの貢献や結果を報酬に反映
このように、評価と報酬を切り分けつつ、適切なつながりを持たせることで、社員の納得感とやりがいを両立させることが可能です。
まとめ|ノーレイティングは「信頼」と「対話」の評価制度
ノーレイティングは、単に評価の“数値”や“ランク”をなくす制度ではありません。それは、社員一人ひとりの成長と向き合い、「対話」と「信頼」をベースにした新しい人事評価の在り方を模索する試みです。
これからの評価制度に必要なのは、点数ではなく“関係性”。「育てる評価」へとシフトする時代の中で、ノーレイティングはその象徴と言えるでしょう。